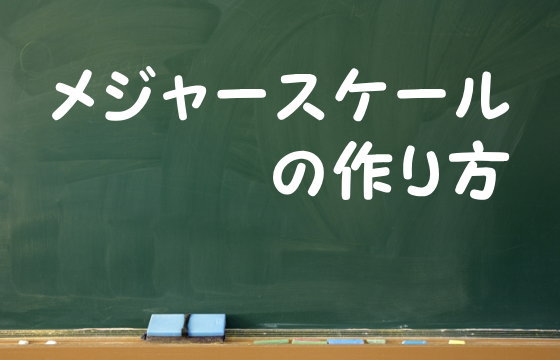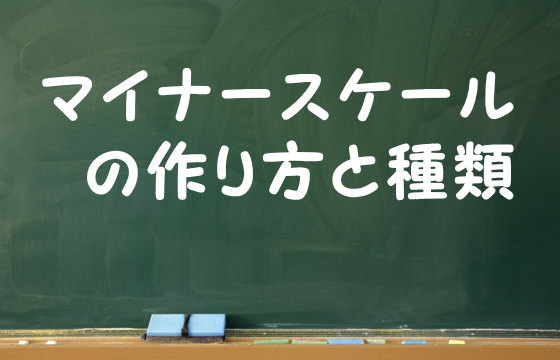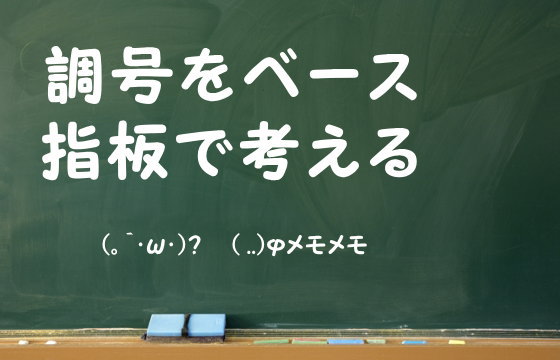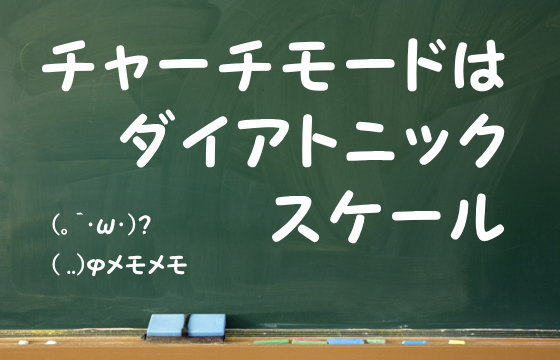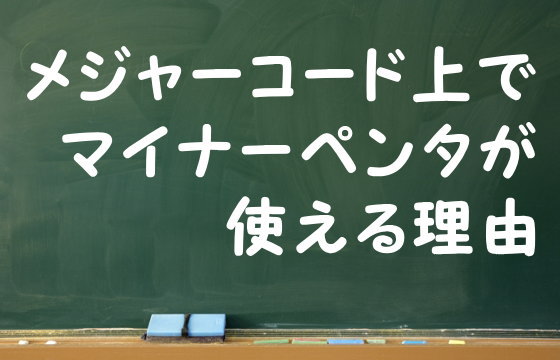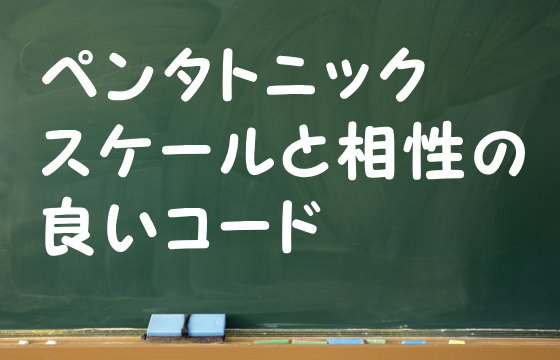ソロアドリブ等のフレーズを作る時、最初に覚えるのがペンタトニックスケール、という場合が多いかと思います。ベースラインにも取り入れ易く、手軽にカッコいいフレーズが考えられる、というのが理由かと思います。ペンタトニックスケールの、作り方から見ていきましょう。
メジャーとマイナーのペンタ
-
Cメジャースケール 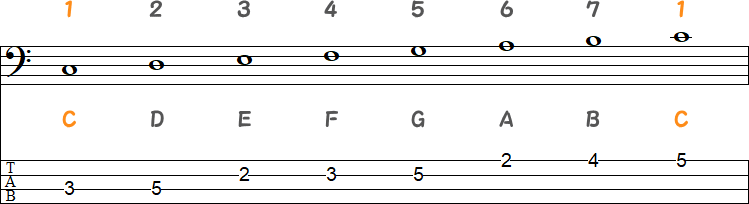
-
Cメジャーペンタトニックスケール 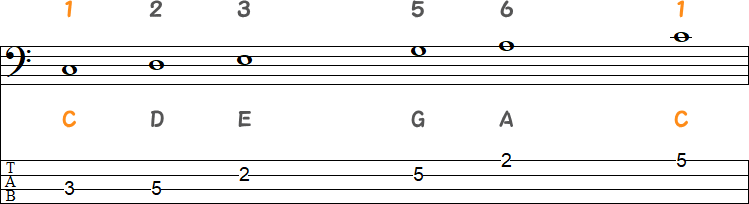
メジャーペンタはヨナ抜き
❶はCメジャースケールで、そこから第4目のFと、第7音目のBを抜くと、❷のCメジャーペンタトニックスケールが作れます。第4・7音目を抜くので、メジャーペンタはヨナ抜き、とも言われます。もちろん、他のメジャースケールからでも、同じ事が言えます。
-
Aマイナースケール 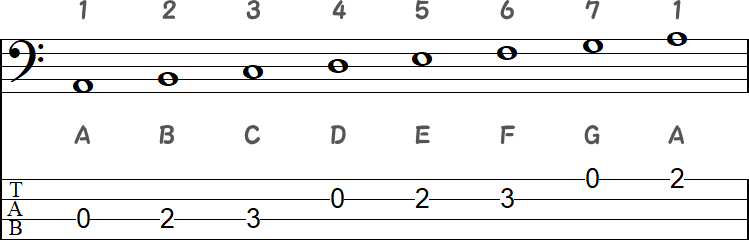
-
Aマイナーペンタトニックスケール 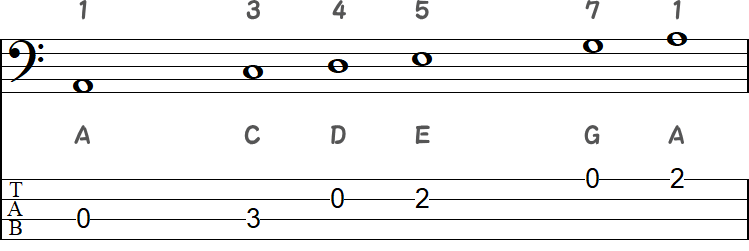
マイナーペンタはニロク抜き
❸はAマイナースケールで、そこから第2音目のBと、第6音目のFを抜くと、❹のAマイナーペンタトニックスケールが作れます。第2・6音目を抜くので、マイナーペンタはニロク抜き、とも言われます。やはり、全てのマイナースケールからでも、ニロク抜きが作れます。
-
Cメジャーペンタトニックスケール 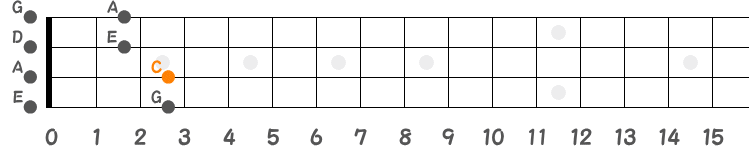
-
Aマイナーペンタトニックスッケール 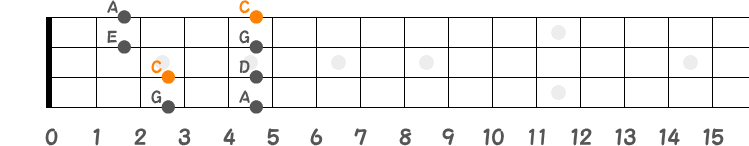
ペンタトニックも平行調
❺がCメジャーペンタ、❻がAマイナーペンタ、のポジションです。両方は●で示す主音は違うものの、構成フレットは同じで、つまりは平行調の関係にあります。これはメジャースケールと、マイナースケールの、平行調の関係と全く同じです。それについては、平行調を参照してください。
大きな譜面を開く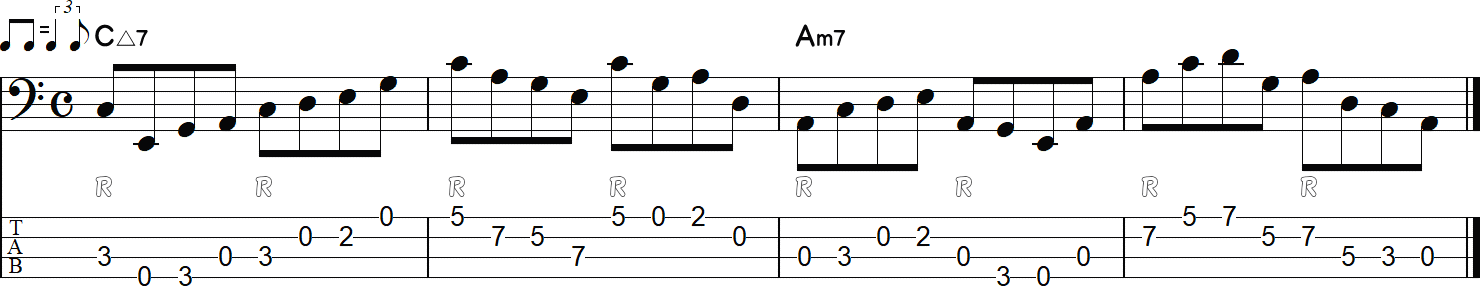
ペンタトニックの使い方
1・2小節目のC△7でCメジャーペンタ、3・4小節目のAm7でAマイナーペンタ、という具合に、コードに合わせたペンタトニックを使う、というの分かると思います。コードのルートを表す![]() も、1・3拍目に置いているので、動きは多いものの、安定したベースラインかと思います。
も、1・3拍目に置いているので、動きは多いものの、安定したベースラインかと思います。
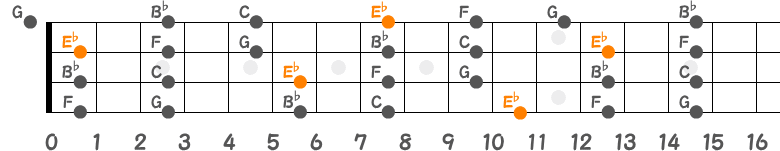
主音を気にし過ぎない
今度は逆に、1・2小節目のC△7でAマイナーペンタ、3・4小節目のAm7でCメジャーペンタ、を使っています。小節の頭に![]() が来ないので、不安になりますが、これでも問題ありません。特にソロでは主音を気にせず、ポジションだけを意識して、テンポよく弾いてやれば、それなり聞こえるものです。
が来ないので、不安になりますが、これでも問題ありません。特にソロでは主音を気にせず、ポジションだけを意識して、テンポよく弾いてやれば、それなり聞こえるものです。
プロ志向のペンタトニック
次からは私が音楽学校で習った、全キーのペンタトニックスケールを、効率よく覚える方法を説明しています。しかし少し複雑で、それなりに大変です。プロを目指すなら、覚えておいた方が良いですが、そうでなければ、覚えずとも全く問題ありません。
ペンタトニックの覚え方
-
Cメジャーペンタトニックスケール(全体) 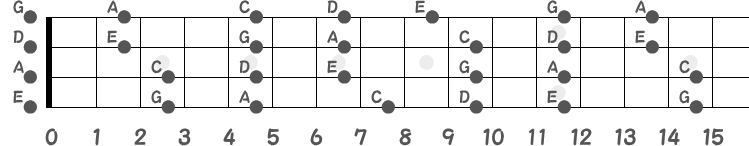
-
Cメジャーペンタトニックスケール(0~3フレット) 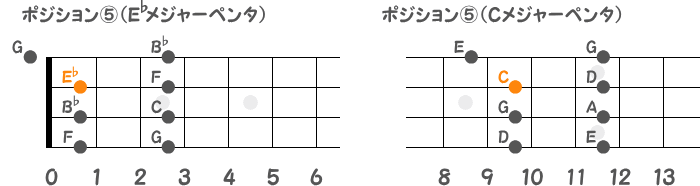
-
Cメジャーペンタトニックスケール(2~5フレット) 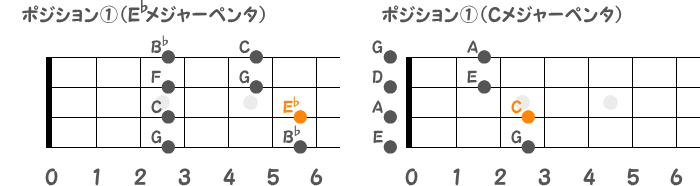
-
Cメジャーペンタトニックスケール(5~8フレット) 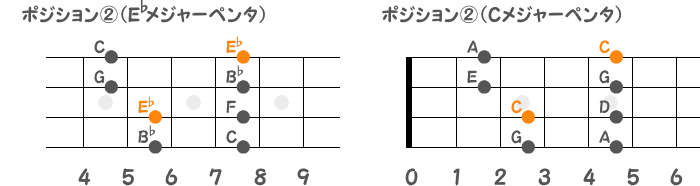
-
Cメジャーペンタトニックスケール(7~10フレット) 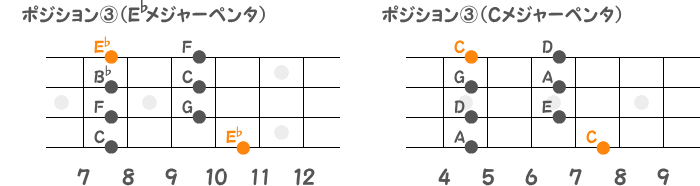
-
Cメジャーペンタトニックスケール(9~12フレット) 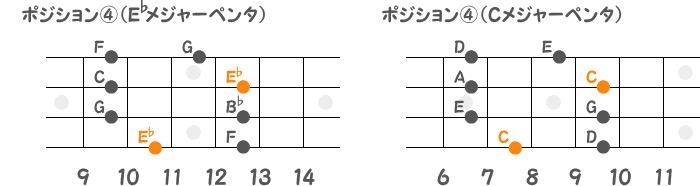
-
Cメジャーペンタトニックスケール(12~15フレット) 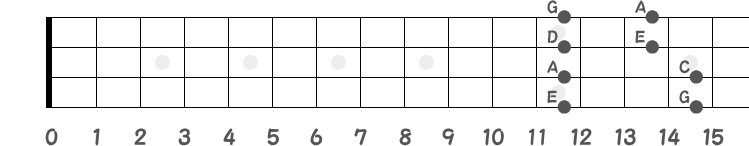
フレット毎に区切る
⓿はCメジャー(Aマイナー)ペンタの、全体的なポジションです。それを❶の0~3フレット、❷の2~5フレット、❸の5~8フレット、❹の7~10フレット、❺の9~12フレット、というフレット毎に区切って覚えます。❻の12~15フレットは、❶と同じポジションなので、全部で5つのポジションが作れます。
ポジションと順番
音名は無理に覚えずともよく、❶~❺の●で作られる、ポジションを覚えてください。次に❶❷❸❹❺という、順番も意識してください。❶から❸や、❷から❺という風に、順番を崩さないという事です。他のキーになると、開始番号は違いますが、連番は維持されます。
-
B♭メジャーペンタトニックスケール 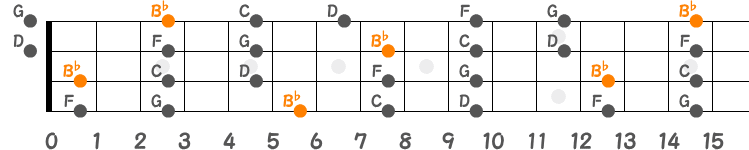
-
Gマイナーペンタトニックスケール 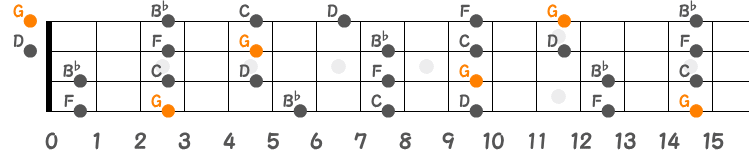
-
B♭メジャー or Gマイナー ペンタトニックスケール 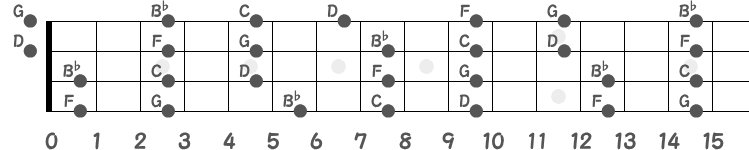
B♭メジャーとGマイナーペンタ
①はB♭メジャーペンタで、②はGマイナーペンタです。両方は平行調なので、主音は違いますが、ポジションは同じです。主音の●を無くしただけの⓪から、先程のように、フレット毎に区切っていきますが、Cメジャー(Aマイナー)ペンタと、比較して見ていきましょう。
-
B♭メジャーペンタ(上)/ Cメジャーペンタ(下)❷のポジション 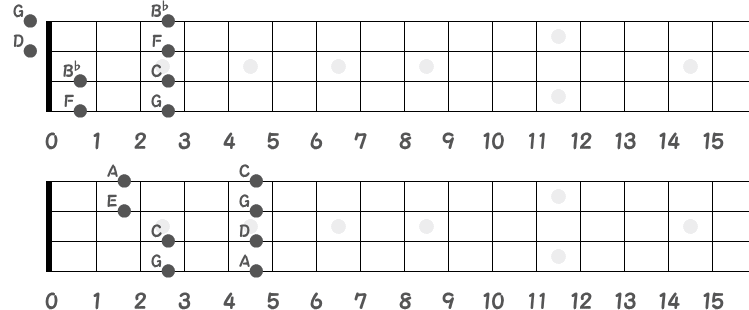
-
B♭メジャーペンタ(上)/ Cメジャーペンタ(下)❸のポジション 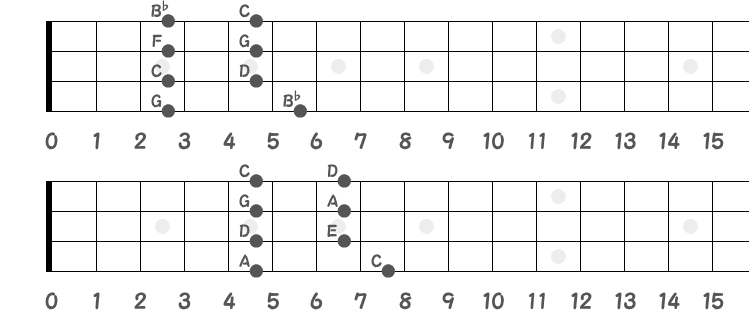
-
B♭メジャーペンタ(上)/ Cメジャーペンタ(下)❹のポジション 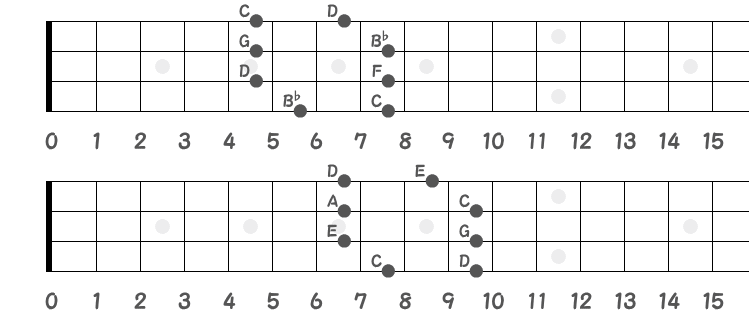
-
B♭メジャーペンタ(上)/ Cメジャーペンタ(下)❺のポジション 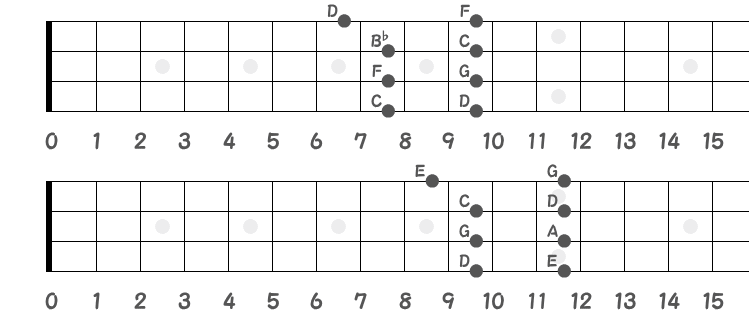
-
B♭メジャーペンタ(上)/ Cメジャーペンタ(下)❶のポジション 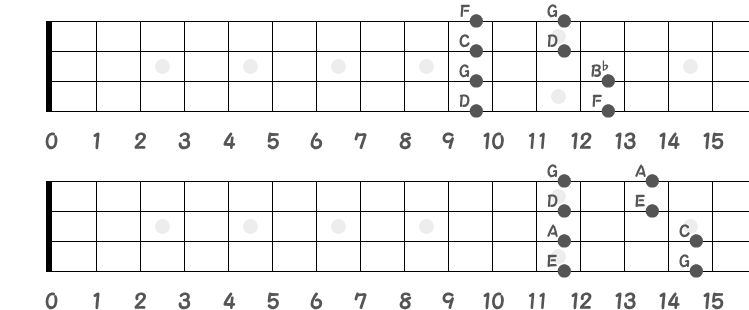
同じポジションで移行する
上の指板図がB♭メジャーペンタで、下の指板図がCメジャーペンタです。押さえるフレットは異なりますが、❷❸❹❺❶と同じポジションを維持して、移行していきます。これはB♭メジャーペンタと、Cメジャーペンタが偶然こうなった、という分けではありません。別のキーでも確認してみましょう。
-
Dメジャーペンタ(上)/ Cメジャーペンタ(下)全体のポジション 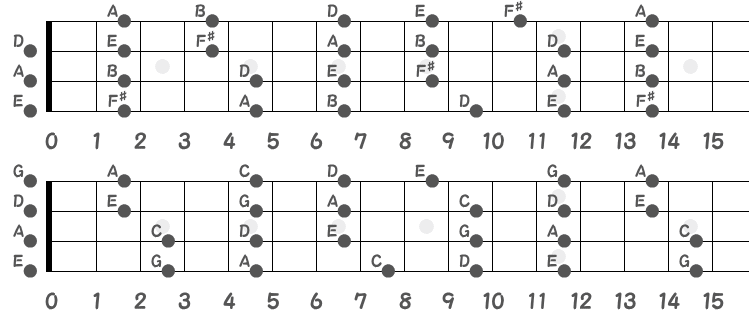
-
Dメジャーペンタ(上)/ Cメジャーペンタ(下)❺のポジション 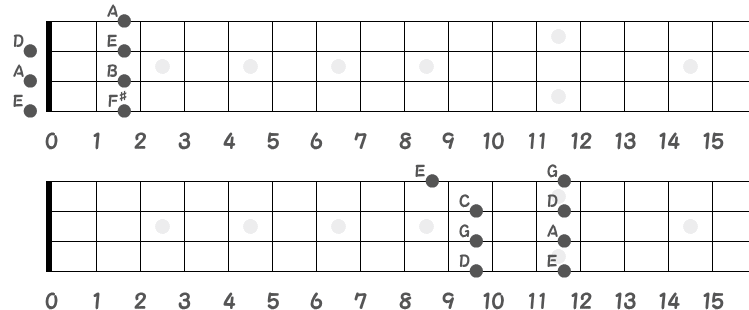
-
Dメジャーペンタ(上)/ Cメジャーペンタ(下)❶のポジション 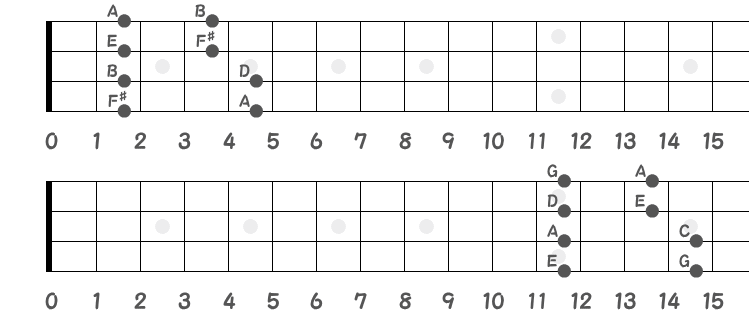
-
Dメジャーペンタ(上)/ Cメジャーペンタ(下)❷のポジション 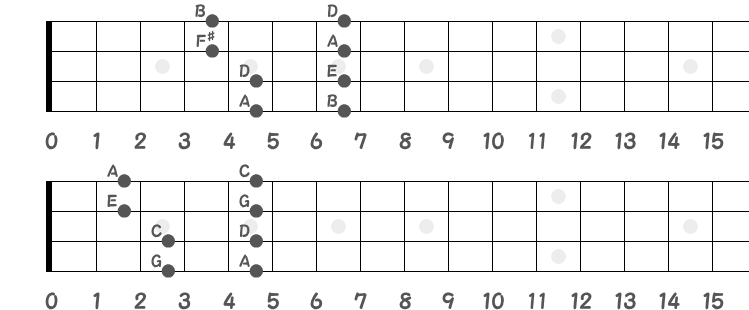
-
Dメジャーペンタ(上)/ Cメジャーペンタ(下)❸のポジション 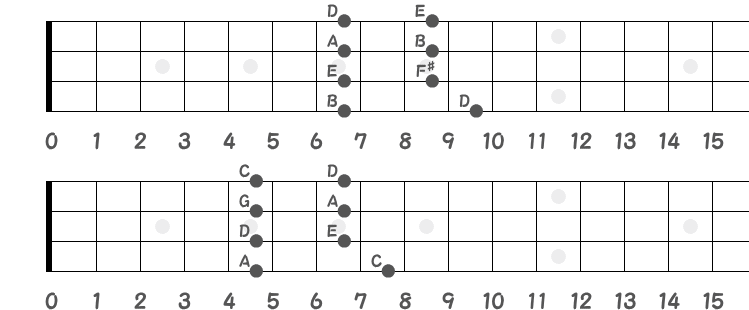
-
Dメジャーペンタ(上)/ Cメジャーペンタ(下)❹のポジション 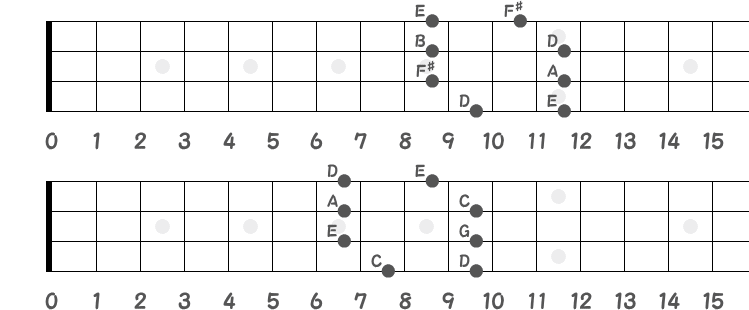
Dメジャーペンタでも同じ
今度の⓿は上の指板図が、Dメジャー(Bマイナー)ペンタで、下の指板図がCメジャーペンタです。これも❺❶❷❸❹という連番で、ポジションが移行していきます。これは全キーのペンタトニックで共通するので、ペタトニックスケール練習をする時の、大きな手助けになると思います。
どういうこと?
上記のペンタトニックの覚え方が、よく分からないというメールを、年に何通か貰います。私の説明下手もあり、ここではこれが限界ですが、前述したように、プロ志向の覚え方なので、そうでない人は次のような、ペンタトニックの覚え方でも、十分かと思います。
-
Aマイナーペンタトニックスッケール(全体) 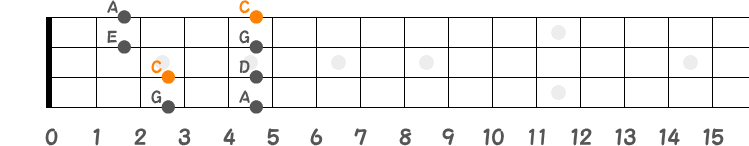
-
Aマイナーペンタトニックスッケール(5~8フレット) 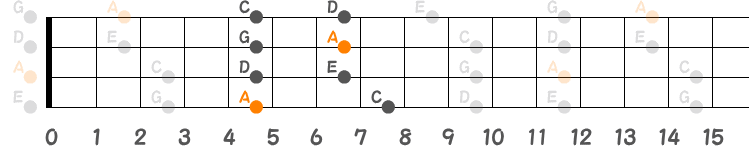
-
Aマイナーペンタトニックスッケール(12~15フレット) 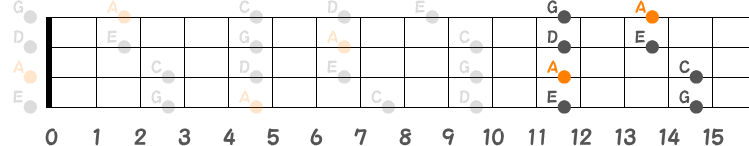
ペンタトニックの範囲を絞る
⓿はAマイナーペンタの、全体的なポジションですが、これを全て覚えようとせず、❸や❶のように、ペンタトニックの範囲を絞って弾く、という方法です。ここでは❸と❶に絞りましたが、自分の好きな範囲を作る、というのも良いでしょう。❸と❶の範囲を使い、簡単なフレーズを弾いてみます。
大きな譜面を開く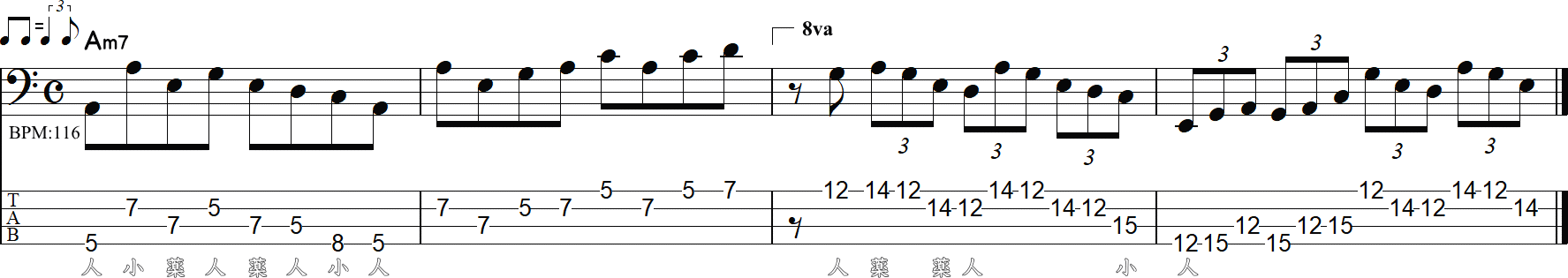
速めに弾くと良い感じ
1・2小節目は❸のポジション、3・4小節目は❶で弾いています。前述もしましたが、ペンタトニックはゆったりと弾くより、少し速弾きしてやる方が、格好よさが際立つかと思います。音源を利用して、Aマイナーペンタのフレーズを、考えてみてください。
マイナーペンタ派が多い?
例えば、平行調同士のCメジャーペンタと、Aマイナーペンタを覚えるとしたら、どちらを意識して覚えますか?数十人しか聞いていませんが、多くはAマイナーペンタを意識する、と答えられました。私もそうで、簡単にいうとマイナーペンタの方が、格好良いフレーズを作り易いからです。
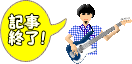
- ペンタトニックにはメジャーとマイナーがある。
- ペンタトニックにも平行調の関係がある。
- ペンタトニックの覚え方は人それぞれ。