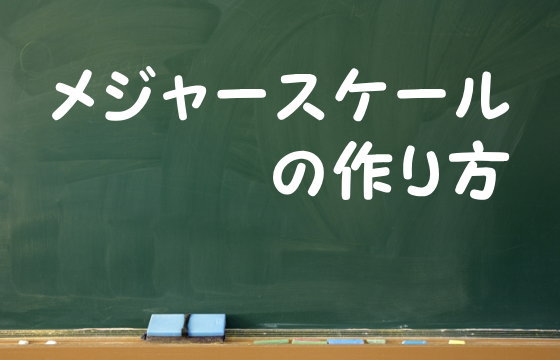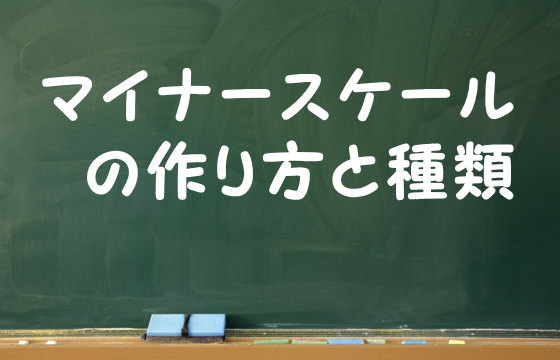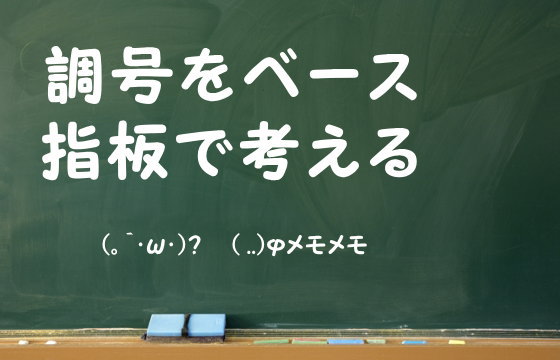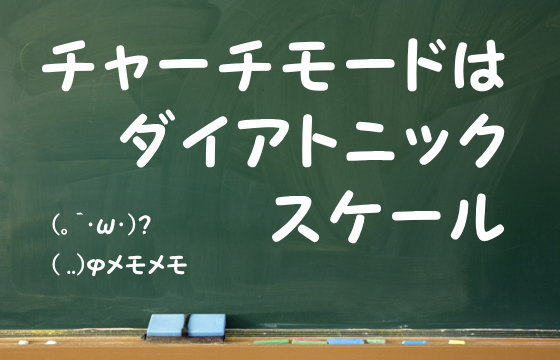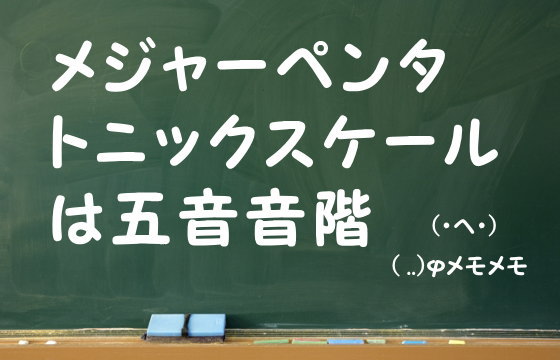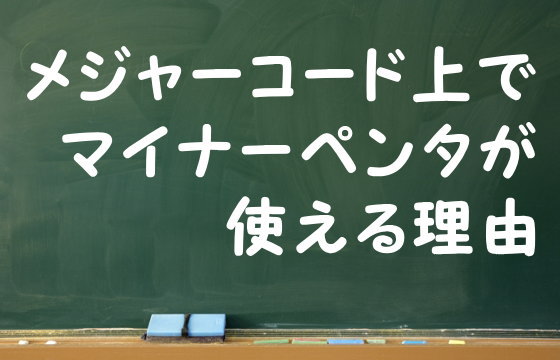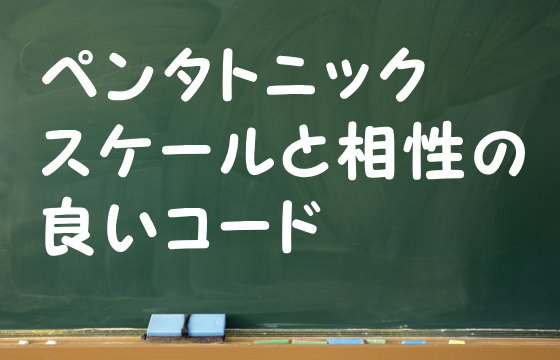例えば、Cメジャースケールの主音を変えて弾くと、それはAマイナースケールになります。これは他のメジャーとマイナーの、スケールにも当てはまり、それぞれがペアのような、関係を持っています。その事を音楽的には平行調(へいこうちょう)と言います。
平行短調と平行長調
長調と短調の音程
| 長調(メジャースケール) | 全音 | 全音 | 半音 | 全音 | 全音 | 全音 | 半音 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短調(マイナースケール) | 全音 | 半音 | 全音 | 全音 | 半音 | 全音 | 全音 |
長調と短調の並び方
上表でも示すように、長調のメジャースケールと、短調のマイナースケールでは、主音からの全音と半音の並び方が異なります。しかし前述した通り、音階の主音を変えてやれば、長調と短調の両方が、一つの音階には見られます。ハ長調のCメジャースケールを、例に挙げて見ていきましょう。
自然のナチュラルが基本
過去のページで三種類の短音階がある、と説明しましたが、ここでは自然的短音階の、ナチュラルマイナースケールで、考えてください。
-
ハ長調(Cメジャースケール) 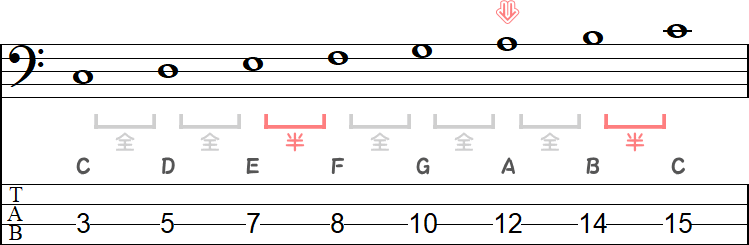
-
イ短調(Aマイナースケール) 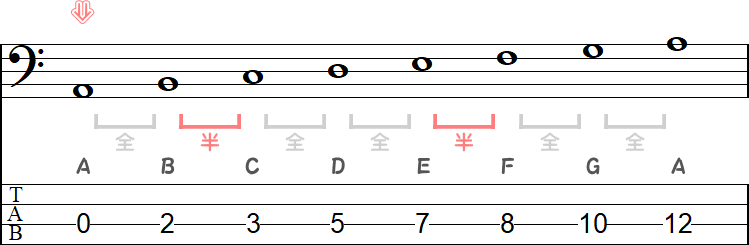
長調の第6音目が平行短調
❶はハ長調ですが、第6音目のAに注目してください。そのAを主音にしたのが❷で、それはイ短調になります。このように、長調の第6音目を主音にすると、その長調の平行調が作れます。また、上記の場合だと、ハ長調の平行短調はイ短調、という言い方もします。
-
イ短調(Aマイナースケール) 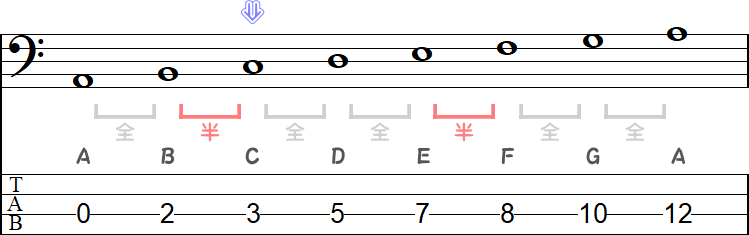
-
ハ長調(Cメジャースケール) 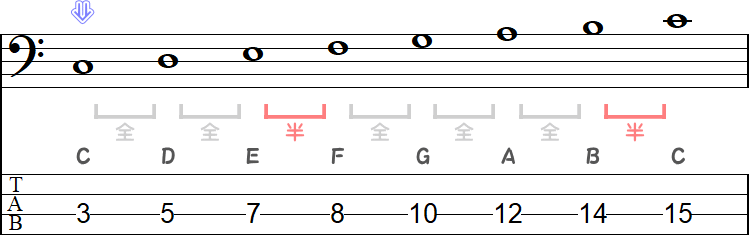
短調の第3音目が平行長調
今度は❸のイ短調から考えてみます。それの第3音目はCですが、そのC音を主音にしてみると、❹のハ長調になります。このように、短調の第3音目を主音にすると、その短調の平行調が出来ます。そして、上記の場合だと、イ短調の平行長調はハ長調、という言い方をします。
-
変ロ長調(B♭メジャースケール) 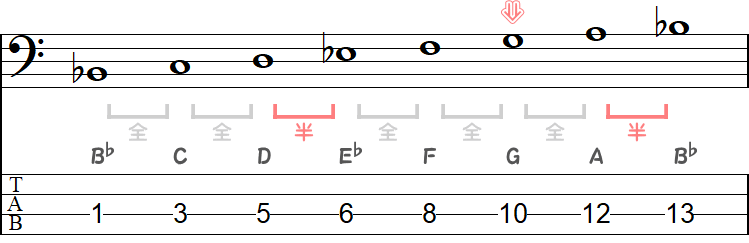
-
ト短調(Gマイナースケール) 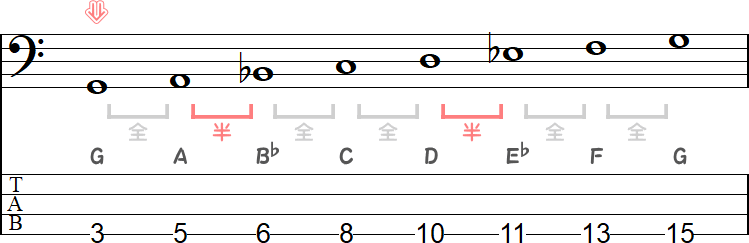
変ロ長調の平行短調は?
❺は変ロ長調で、それの第6音目はGです。そのGを主音にした❻が、変ロ長調の平行短調であるト短調、という事になります。変ロ長調もト短調も、主音が違うだけで、同じ構成音で作られます。
変と嬰
日本式でフラットを変(へん)と言い、シャープを嬰(えい)と言います。
-
嬰ハ短調(C#マイナースケール) 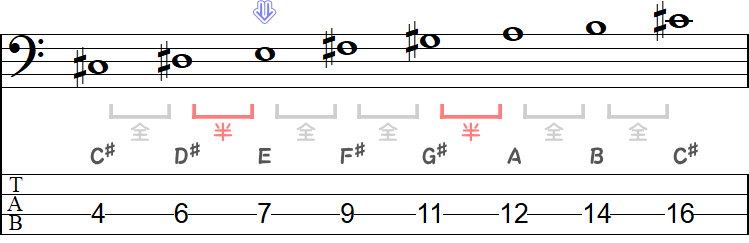
-
ホ長調(Eメジャースケール) 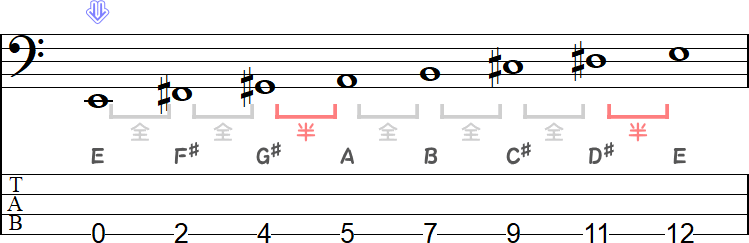
嬰ハ短調の平行長調は?
❼は嬰ハ短調で、それの第3音目はEです。そのEを主音にした❽が、嬰ハ短調の平行長調であるホ長調、という事になります。やはり嬰ハ短調とホ長調は、主音違いの同じ構成音です。
曲は長調と短調が共存する
例えば、ハ長調で始まった曲があるとします。ハ長調にはイ短調も含まれるので、曲中にイ短調になったり、イ短調で終わる事もあります。このように、長調と短調は共存関係にあります。覚える必要はありませんが、♭が付く平行調と#が付く平行調を、サラッと確認しておきましょう。
-
Cから半音3つ下のA 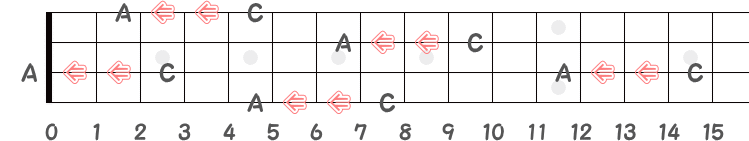
-
Aから半音3つ上のC 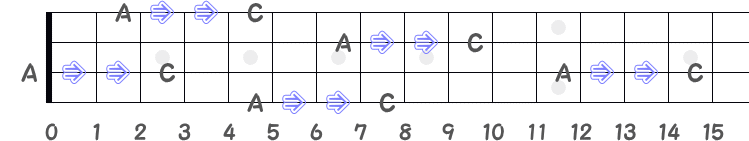
ベース指板で見る平行調
Cメジャーの平行調を探すとします。先ず指板の音名からCを見つけ、そこから3つ下のフレットが、❾の平行短調の主音Aになります。逆に、Aマイナーの平行調を探すなら、指板の音名のAから、3つ上のフレットのCが、❿の平行長調の主音Cになる分けです。他の長調と短調でも、試してみましょう。
平行調は転調の一種
平行調は曲中に、キーを変える時に使用され、その事を転調(てんちょう)と言います。転調は平行調だけではなく、他にも以下で説明する種類があります。作曲に興味があるなら、知っておくと良いですが、ベースを弾くだけなら、平行調さえ知っておけば、良いとも思います。
近親調
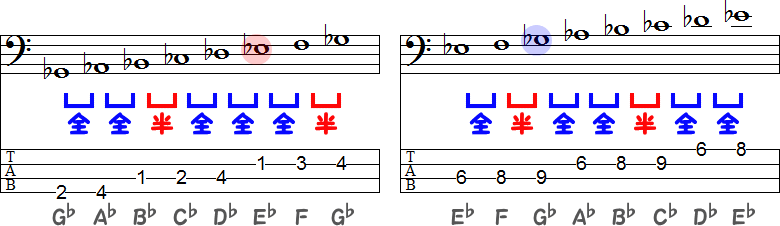
主調や基調は曲の中心
調というのは音の高さの事で、英語ではKey(キー)という言葉に相当します。曲の中心になる調を主調(しゅちょう)や、基調(きちょう)と言い、それだけで終える曲もあれば、前述した転調を行い、曲の雰囲気を変える事もあります。ここでは主調をハ長調として、転調を考えていきましょう。
-
下属調のヘ長調(Fメジャーキー) 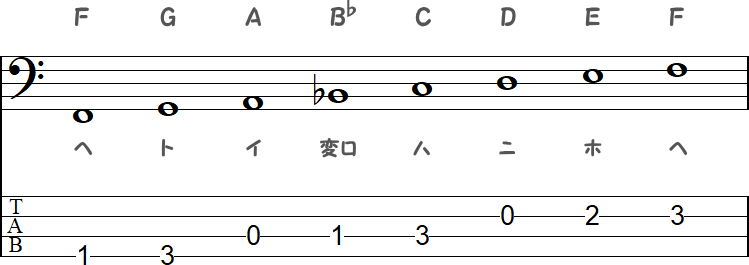
-
属調のト長調(Gメジャーキー) 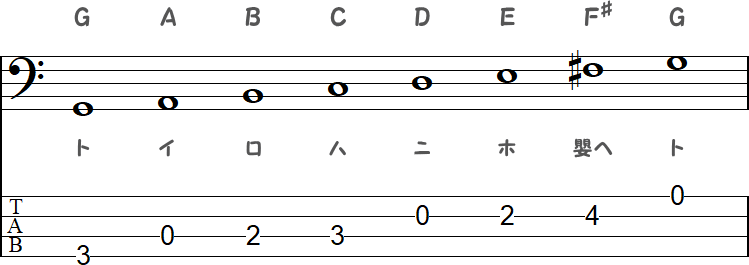
-
平行調のイ短調(Aマイナーキー) 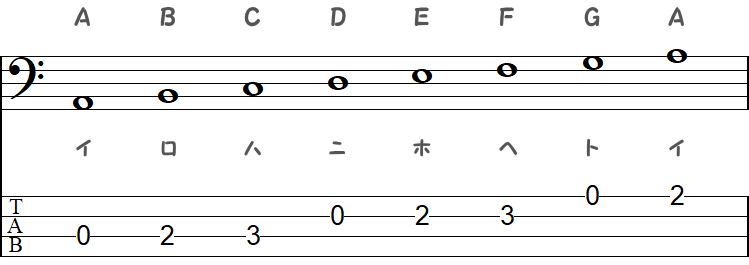
-
同主調のハ短調(Cマイナーキー) 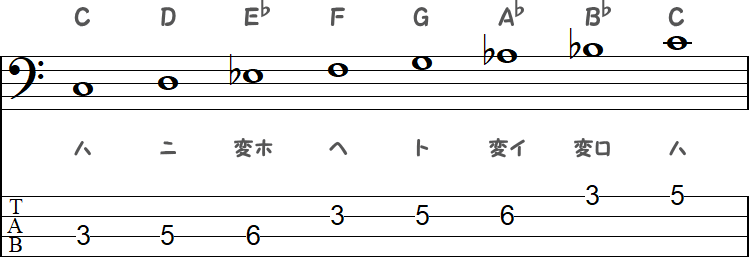
近親調は転調し易い
転調する調に決まりはありませんが、転調し易い調というのがあり、それを近親調(きんしんちょう)と言います。❶~❹が主調をハ長調とする近親調です。順番に確認していきましょう。
- 下属調(かぞくちょう)
主調の第4音目を、主音にした音階が下属調です。主調が短調だと、下属調も短調になります。
- 属調(ぞくちょう)
主調の第5音目を、主音にした音階が属調です。同じく主調が短調だと、属調も短調になります。
- 平行調(へいこうちょう)
長調の第6音目を、主音にする音階が平行短調で、短調の第3音目を、主音にする音階が平行長調です。平行調同士は同じ音名を持つ音階です。
- 同主調(どうしゅちょう)
同じ主音を持つ長調と短調を、同主調と言います。例えば、主調がハ長調なら同主調はハ短調、主調がハ短調なら同主調はハ長調、という具合です。
主調をハ長調とする近親調の構成音
| 主調のハ長調 | C | D | E | F | G | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下属調のヘ長調 | F | G | A | B♭ | C | D | E | F |
| 属調のト長調 | G | A | B | C | D | E | F# | G |
| 平行調のイ短調 | A | B | C | D | E | F | G | A |
| 同主調のハ短調 | C | D | E♭ | F | G | A♭ | B♭ | C |
近親調は構成音が似る
主調のハ長調は♭や#の、派生音が一つも無い音階です。近親調は派生音を含みますが、比較的、主調と似た構成音なので、転調し易いとされています。近親調の逆を遠隔調(えんかくちょう)と言い、曲調をガラリと変えたい場合などは、そこへ転調される事もあります。
移調は全体的に変える
例えると、転調は曲の箱だけを変えるのに対し、箱の中身も全て変える、というのを移調(いちょう)と言います。それは姉妹サイトの、転調と移調で説明しています。
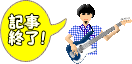
- 平行調は同じ構成音。
- 平行調は転調の一つとして使われる。
- 近親調や遠隔調は作曲に興味が沸いたら覚える。