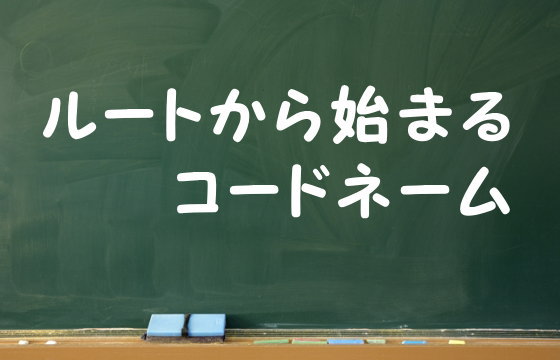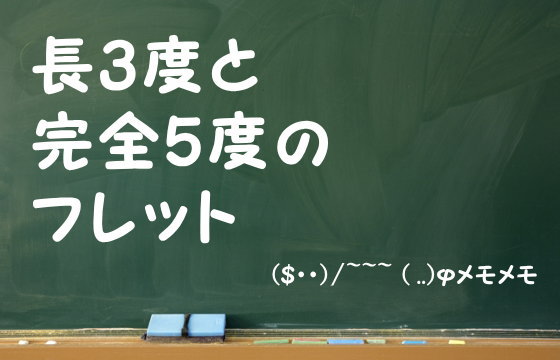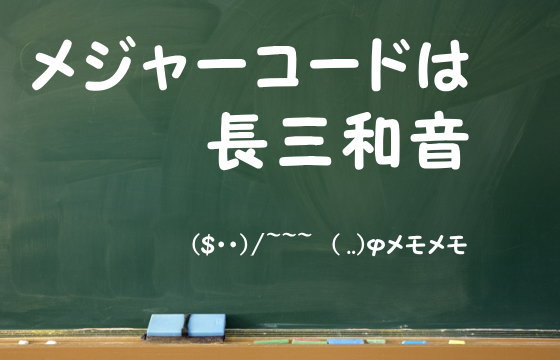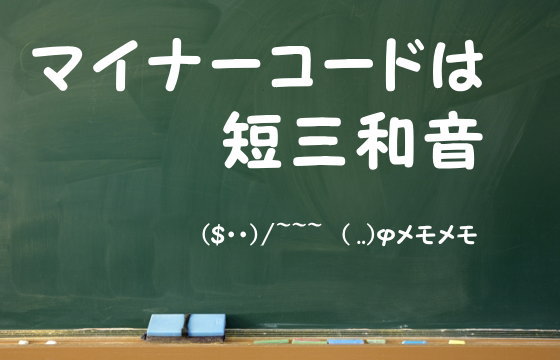エレキベースのコードを知る前に、先ずはコードの基本的な作られ方、を知っておきましょう。コードはスケールを元に作られるので、ここではCメジャースケールから考えていきます。そして、ベーシストがコードの構成音の中で、最も気にするRoot(ルート)についても、知っておきましょう。
コードとRoot
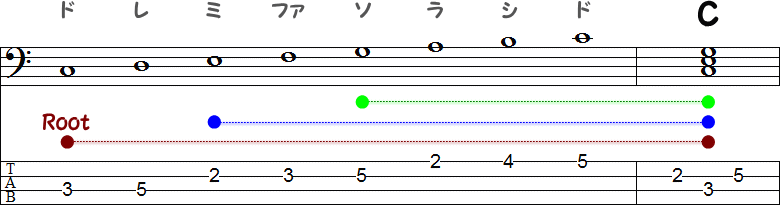
コードの基本構成
1つ目が3弦3フレットのド、2つ目が2弦2フレットのミ、3つ目が2弦5フレットのソというように、コードはスケールを一音ずつ飛ばして、積み重ねて作るのが基本です。そして、コードの最低音をRootと言い、ベーシストは主にRootを弾く、というのが基本と思ってください。
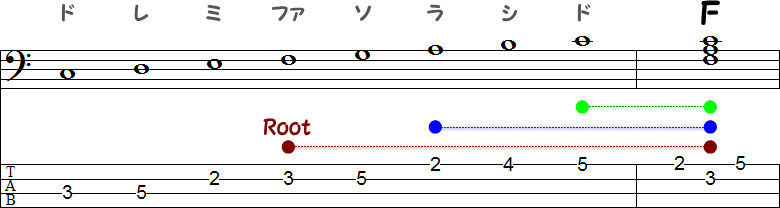
根音とRootは同じ意味
次は1つ目が2弦3フレットのファ、2つ目が1弦2フレットのラ、3つ目が1弦5フレットのドで、やはり一音ずつ飛ばして、コードが完成しています。そして、Rootを日本式では根音(こんおん)と言います。根音もRootと同じくらい耳にするので、しっかり覚えておきましょう。
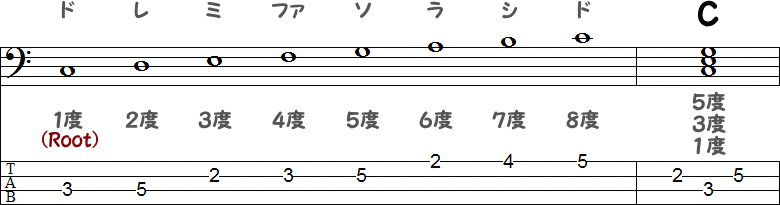
Rootの略記号
Rootに関しての、まとめをしておきましょう。上表のようにRootは、頭の文字を取って![]() と略される事も多いです。同じく上表に
と略される事も多いです。同じく上表に![]() という記号がありますが、これは半音を表しています。分かり易いように、ベースの指板で見ていきましょう。
という記号がありますが、これは半音を表しています。分かり易いように、ベースの指板で見ていきましょう。
-
Rから半音1つの☆ 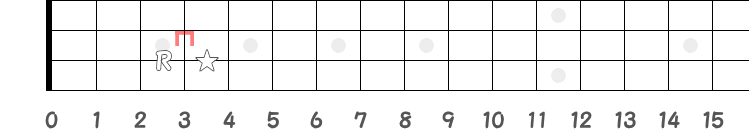
-
Rから半音2つの☆ 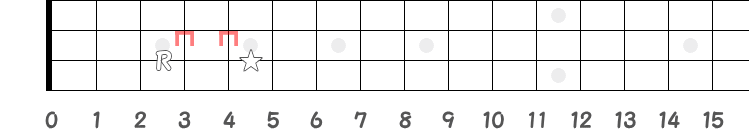
-
Rから半音3つの☆ 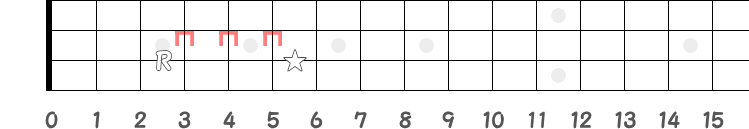
-
Rだけの半音0 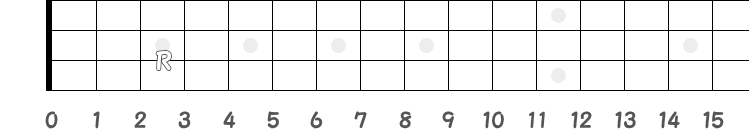
半音はフレット1つ分
❶❷❸は![]() が3弦3フレットにありますが、それぞれ☆までの半音の数が、1フレットずつ違っています。つまり半音はフレット1つ分という事で、最小の距離とでも覚えておきましょう。そして、⓿のように
が3弦3フレットにありますが、それぞれ☆までの半音の数が、1フレットずつ違っています。つまり半音はフレット1つ分という事で、最小の距離とでも覚えておきましょう。そして、⓿のように![]() だけなら、半音の数は存在しません。
だけなら、半音の数は存在しません。
度数(どすう)
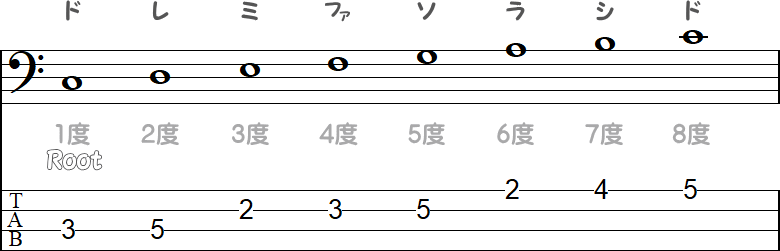
1度から始まる
音符から音符の距離を音程と言いますが、その時に用いるのが度数(どすう)という単位です。始まりのドを1度として、音符が1つ上がる毎に、2度・3度・4度と上がっていきます。始めの1度ですが、これはRootと同じと思っても良いでしょう。
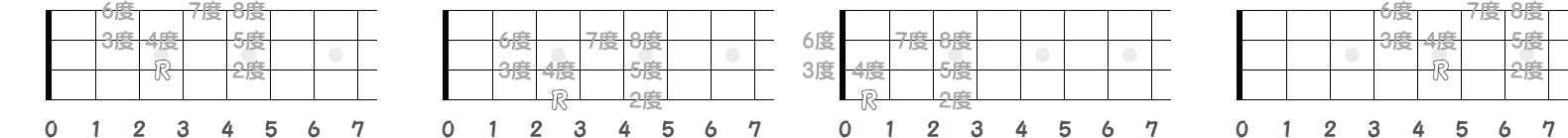
Rootからの度数は一定
ベースの指板に度数を置いてみると、上記のような感じです。4つの指板を見比べてみると、どれも同じ距離関係を保っているのが分かります。このように![]() からの度数は、いつでも一定の距離を保ちます。
からの度数は、いつでも一定の距離を保ちます。
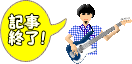
- コードはスケールを元に、一音飛ばしで作られるのが基本。
- コードの最低音をRootと言い、日本式では根音と言う。
- 音程の単位は度を使い、一定の距離を保つ。