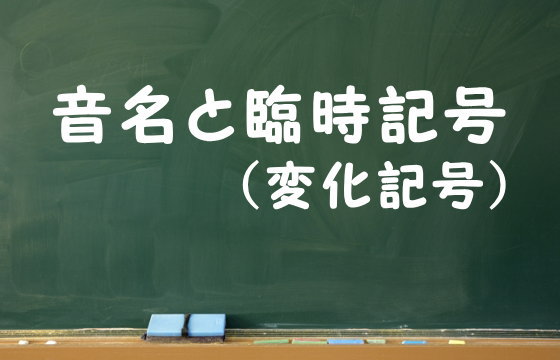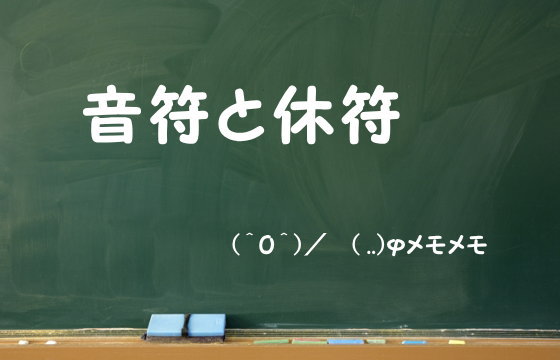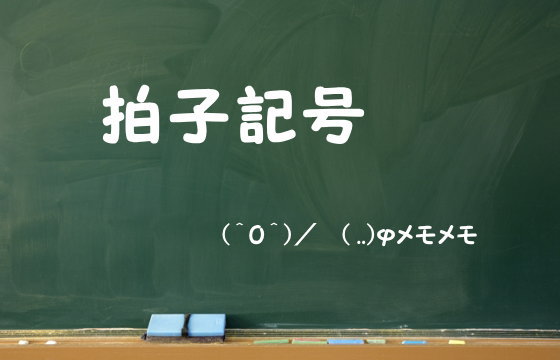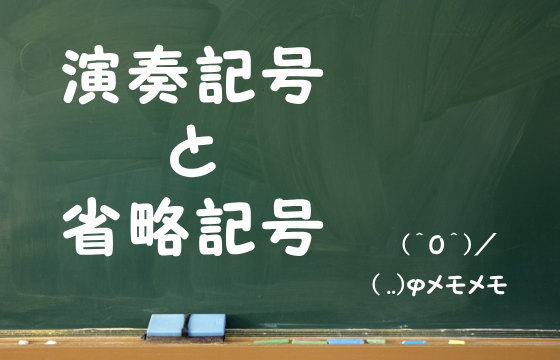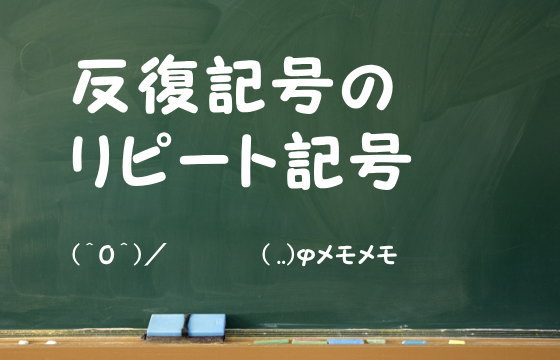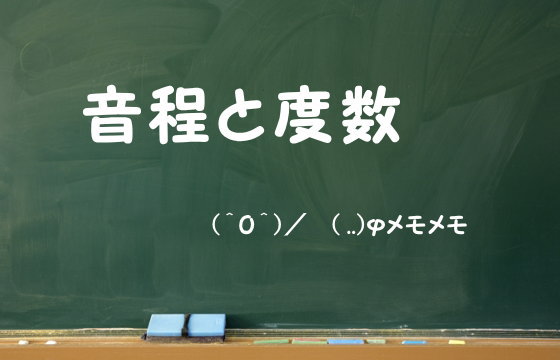小節を例えるなら、音符や休符を入れる箱で、その箱に区切りを付け、分かり易くするのが小節線(しょうせつせん)です。また、譜面の最初には音部記号(おんぶきごう)という、音の高さを決める記号があります。小節線と音部記号の、最も基本的な事だけ確認します。
小節線
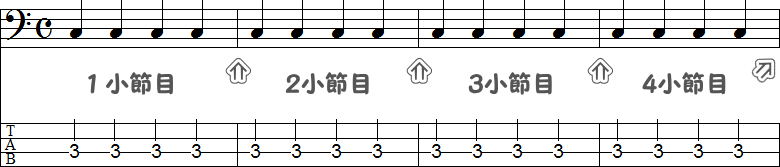
縦線が最も多い
矢印でも示す縦一本の線を、縦線(じゅうせん)と言いますが、これを小節線と呼ぶ場合が多いです。この縦線で区切っていき、左から1・2・3・4小節目、という風にして呼びます。
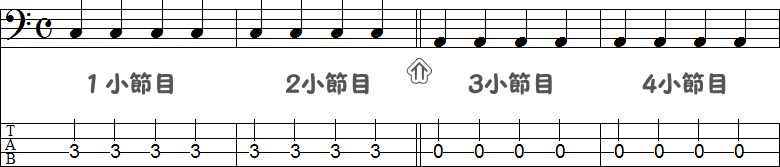
複縦線で場面を変える
2小節目のような縦二本の線を、複縦線(ふくじゅうせん)と言います。複縦線はイントロからAメロ、AメロからBメロ、Bメロからサビなど、場面を変える時に使う小節線です。
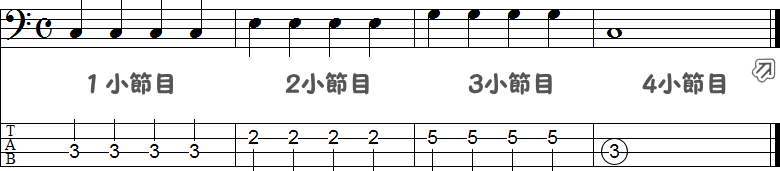
終止線で曲を終える
4小節目のような縦線と太線を、終止線(しゅうしせん)と言います。その名の通り曲を終える小節線で、譜面の終わりは終止線を書く、というのが決まりです。
小節線は他にもある
クラシック音楽なら他にも、少し複雑な小節線を使いますが、ポピュラー音楽なら、これら三種類の小節線を覚えておけば、先ず困る事はないでしょう。
音部記号
-
ヘ音記号 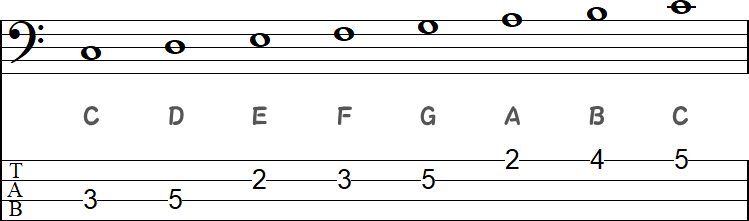
-
ト音記号 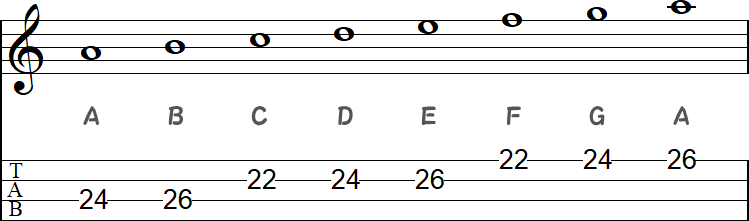
ベースはヘ音記号
❶の音部記号をヘ音記号と言い、低音域の楽器に使われます。❷の音部記号をト音記号と言い、高音域の楽器に使われます。私たちベーシストは低い音を扱うので、ヘ音記号を使います。上記の両方は、音符の位置は同じですが、音名やTAB譜を見比べると、全く違うのが分かります。
-
ヘ音記号とト音記号(オクターブ) 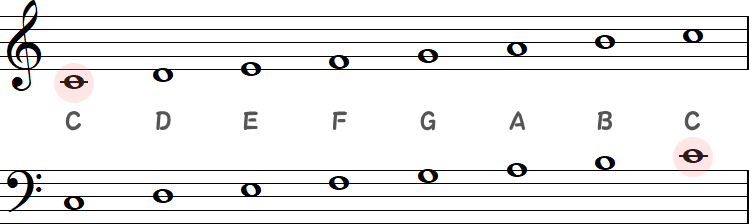
-
ヘ音記号とト音記号(移動) 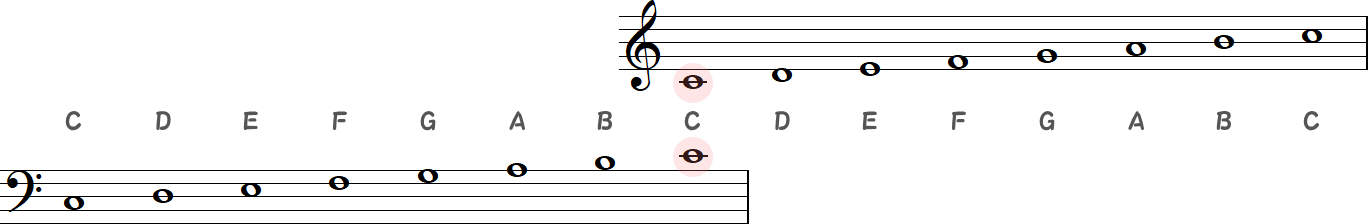
ヘ音記号とト音記号の見比べ
❸の音符を縦に見ると、丁度オクターブの差があります。ヘ音記号の最後のCと、ト音記号の最初のCが同じ高さのCで、分かり易く表すと、❹のように見る事も出来ます。しかし、TAB譜を見るに限っては、ヘ音記号もト音記号も関係ないので、分からなくても問題ありません。
ハ音記号もある
他にもハ音記号という音部記号もあり、それは姉妹サイトの、音部記号で説明していますが、滅多に出てこないので、覚えなくても大丈夫です。
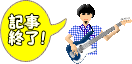
- 縦線・複縦線・終止線が基本の小節線。
- ヘ音記号とト音記号が基本の音部記号。
- TAB譜を見るなら音部記号は関係ない。