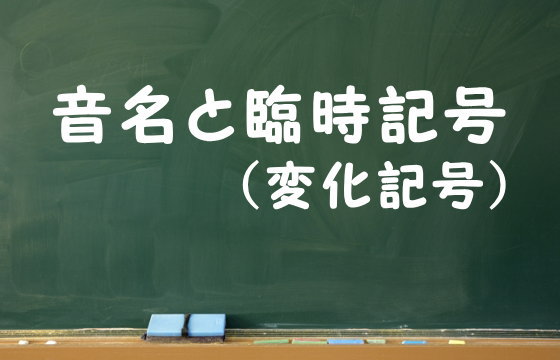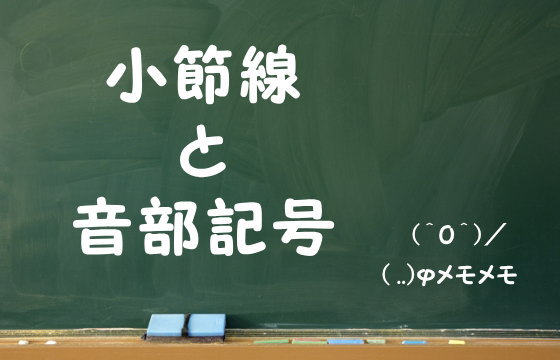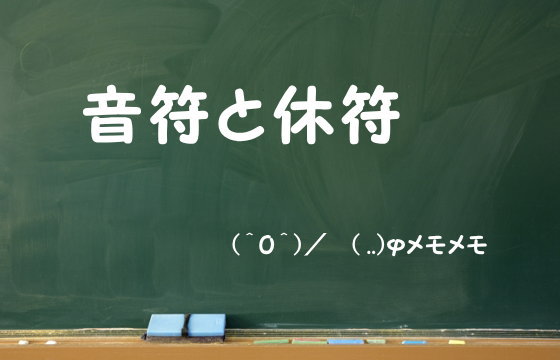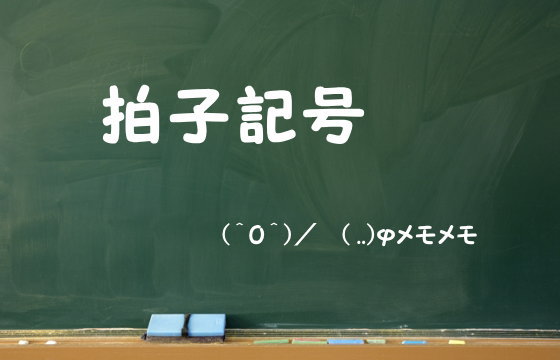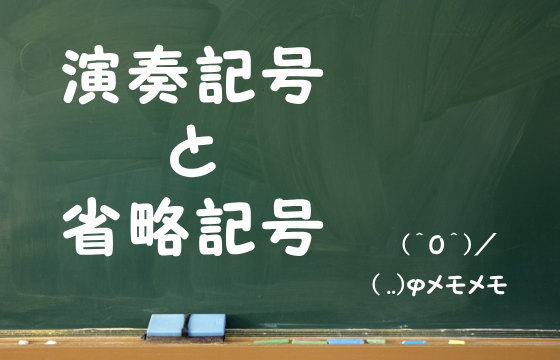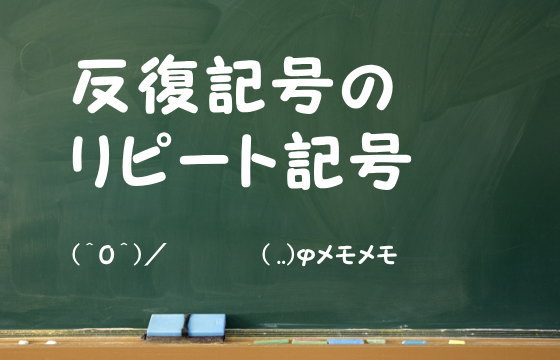音から音への距離を音程(おんてい)と言い、音程には幾つかの種類があります。物差しやメジャーで距離を測ると、センチやメートルといった単位があるように、音程では度(ど)という単位を使います。基本的な音程の呼び方と、音程の種類を見ていきましょう。
音程の基本
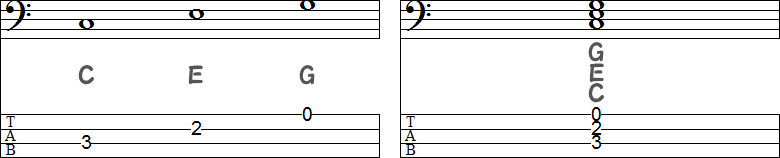
旋律と和声の音程
音を一音ずつ鳴らす事を旋律的音程と言い、メロディと思えば良いでしょう。同時に鳴らすと和声的音程と言い、分かり易くはコード弾きの事です。鳴らし方に違いはあるものの、音楽を聞いたり演奏したりするには、この音程を感じる事が非常に重要です。
-
Cメジャースケール(3弦3フレット~1弦5フレット) 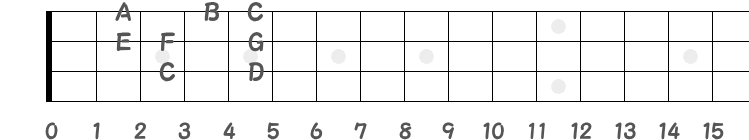
-
1度~8度(3弦3フレット~1弦5フレット) 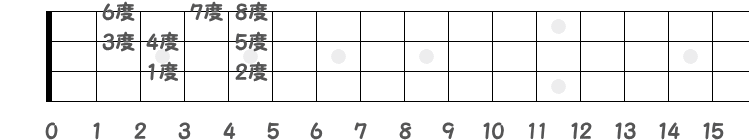
-
1度~8度(3弦3フレット~3弦15フレット) 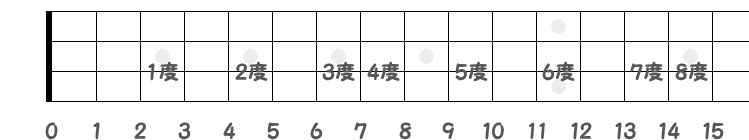
Cメジャースケールの度数
❶は3弦3フレットから始まる、Cメジャースケールです。これを度数(どすう)に置き換えると❷のように、3弦3フレットのCを1度とし、以下はDが2度、Eが3度、といった具合になります。数字が大きいほど、1度からの音程が広いので、異弦同音で表した❸のように見ると、より分かり易いかと思います。
-
4弦2フレットを1度とする度数 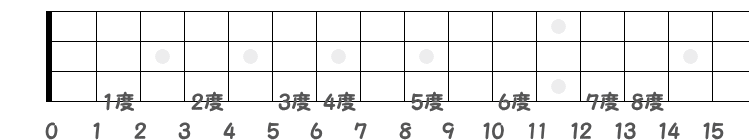
-
2弦1フレットを1度とする度数 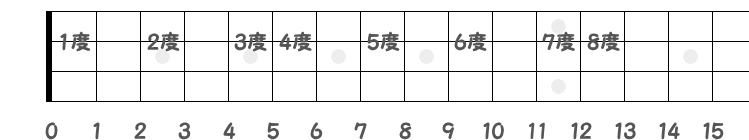
-
1弦0フレットを1度とする度数 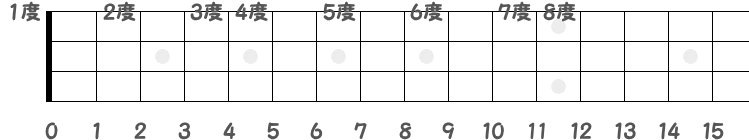
度数は一定を保つ
1度が他のフレットになっても、度数は一定の距離を保ちます。❹~❻を見ても、先程の3弦3フレットを1度とする度数が、全体的に同じ距離を保って、移動しているのが分かると思います。
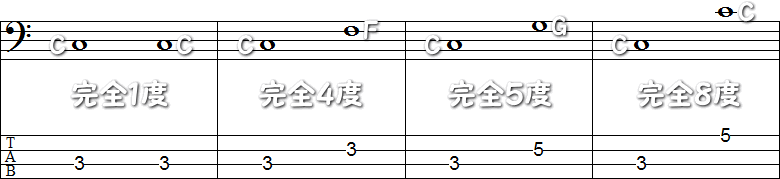
同じ音程は0度ではない
Cメジャースケールに戻し、今度は二音ずつで考えてみます。3弦3フレットのCを基準にすると、2度以降の度数は説明した通りですが、同じ3弦3フレットのCとの音程は、0度ではなく1度として数えます。度数に0度以下はないので、覚えておきましょう。
度数は9度以上もある
度数には9度以上もありますが、先ずは8度以下を知っておけば大丈夫です。因みに、8度までを単音程(たんおんてい)、9度以上を複音程(ふくおんてい)と言います。
度数の冠(かんむり)
-
1度(C) 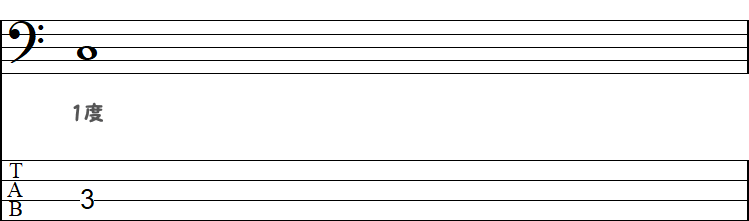
-
2度(C~D) 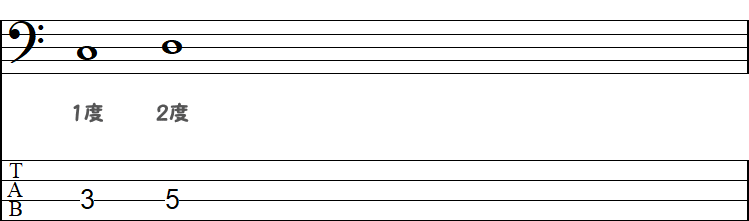
-
3度(C~E) 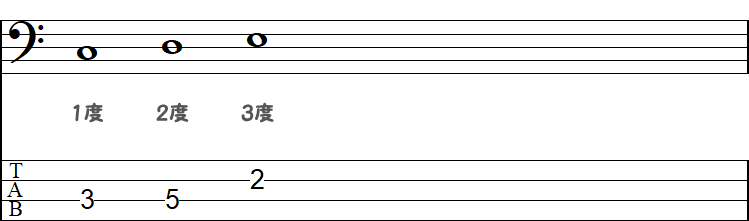
-
4度(C~F) 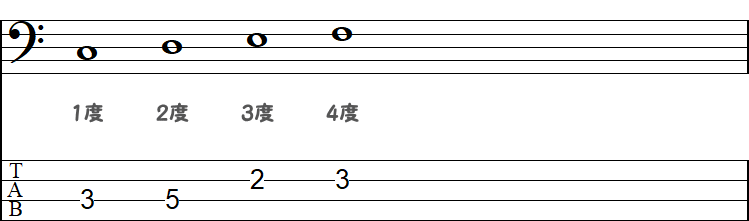
-
5度(C~G) 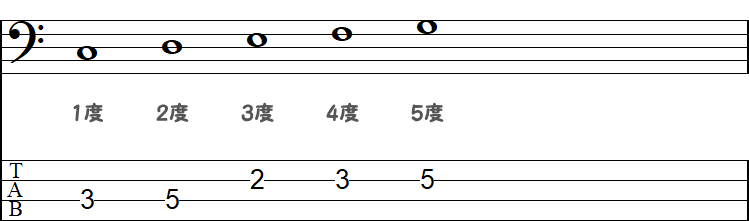
-
6度(C~A) 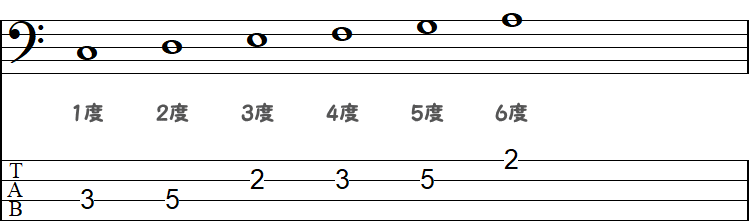
-
7度(C~B) 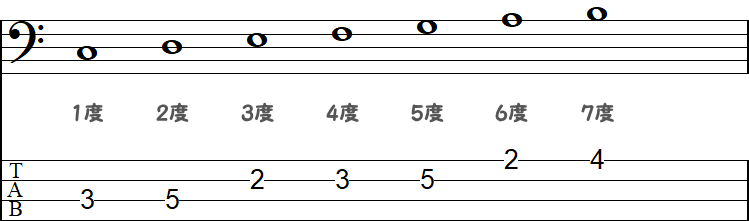
-
8度(C~C) 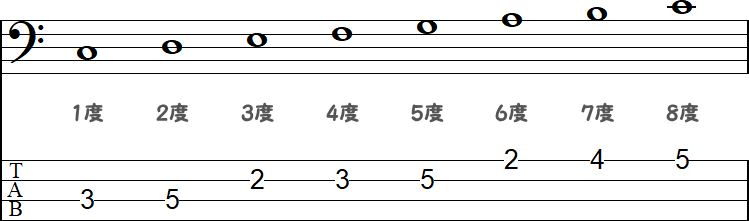
度数の数え方は音符
ここからは音符に注目してください。❶を1度とした時、音符が1つ上がった❷が2度、もう一つ音符が上がった❸が3度というように、音符が順番に上がっていく毎に、度数も1度ずつ増えます。これを踏まえて、度数の種類について考えていきましょう。
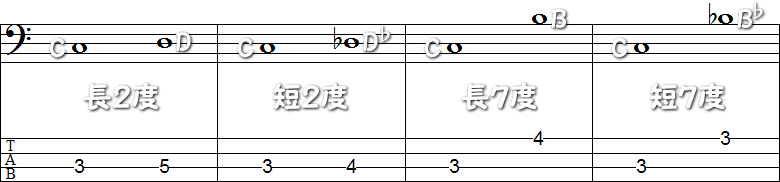
長と短で区別する
度数だけを見れば、左右の小節は7度ですが、左はBで右はB♭という違いがあります。両方を同じ7度と呼ぶと都合が悪いので、昔の人は左を長7度とし、右を短7度として区別しました。名前の通り長7度の方が、短7度より距離が長い、詰まりは音程が広い、というのが分かるでしょうか。
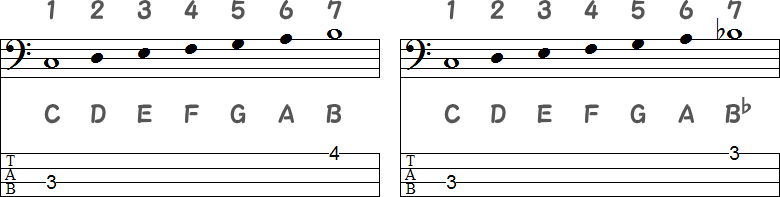
3度も長短で区別する
次も度数だけでは、どちらも3度です。しかし、右はE♭なので、やはり両方を3度と呼ぶと、ややこしくなります。これも同じように、音程の広い左を長3度と、音程の狭い右を短3度と呼んで区別します。
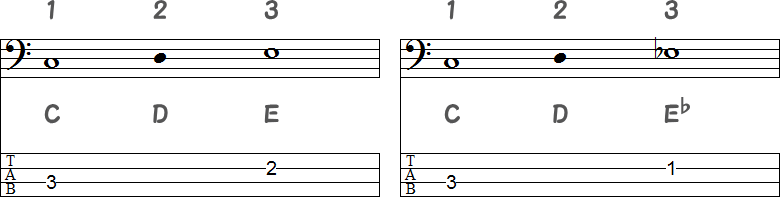
完全音程から減音程
左小節は5度ですが、これを正しくは完全5度と言います。右小節も5度ですが、G♭とあるので、完全5度ではありません。完全音程から半音狭くなると、減音程というものになり、右を減5度と言います。
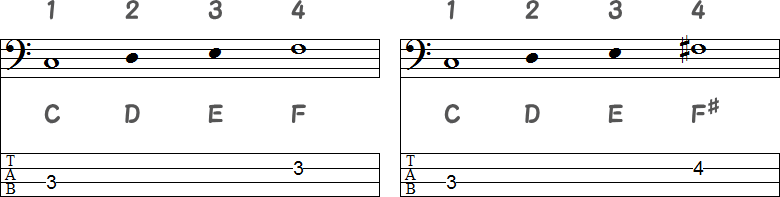
完全音程から増音程
左小節は先程も見た完全5度です。右小節を今度はG#としてあり、半音広がった状態です。完全音程から半音広がると、増音程というものになり、右を増5度と言います。
-
長2度・長3度・長6度・長7度の長音程 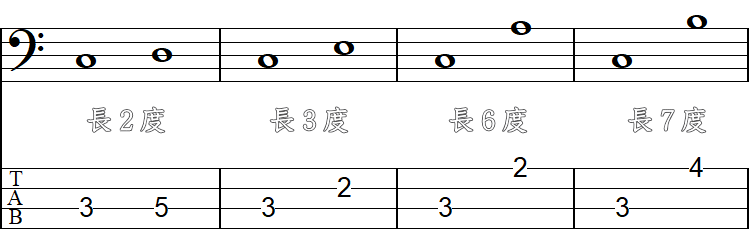
-
短2度・短3度・短6度・短7度の短音程 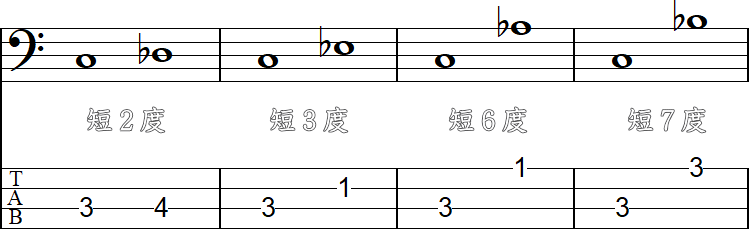
長短の冠を付ける度数
3度と7度だけではなく、2度と6度にも長短の冠を付けて、音程の区別をします。長3度・短3度・長6度・短6度は不完全協和音程と言われ、まずまず溶け合う音程とされます。長2度・短2度・長7度・短7度は不協和音程と言われ、音がぶつかり濁る音程です。❾と❿の音源でも確認しておきましょう。
-
減4度・減5度・減8度の減音程 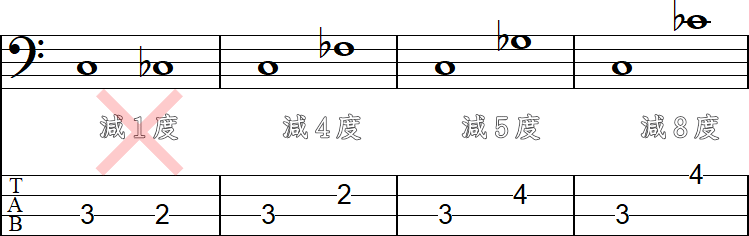
-
完全1度・完全4度・完全5度・完全8度の完全音程 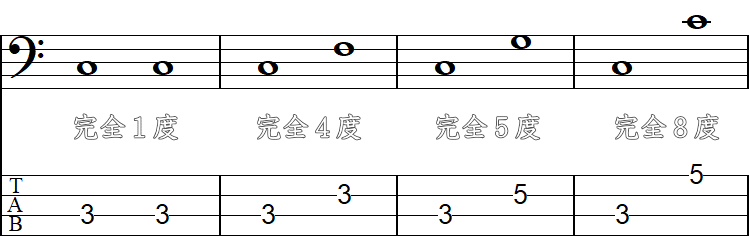
-
増1度・増4度・増5度・増8度 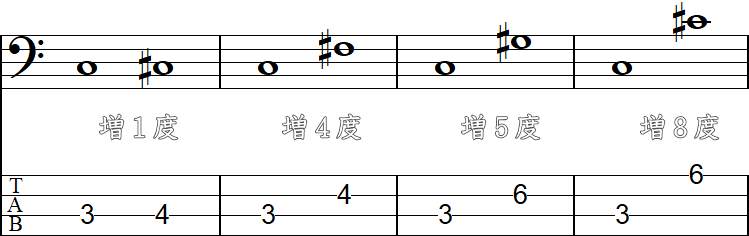
完全の冠を付ける度数
⓬で見られる5度だけでなく、1度と4度と8度にも完全の冠を付けます。これらは完全協和音程と言われ、透き通り綺麗に聞こえる音程です。ここから半音狭くなると⓫の減音程、半音広くなると⓭の増音程となる分けです。ただ、音程は完全1度が最も狭いので、減1度という音程はありません。
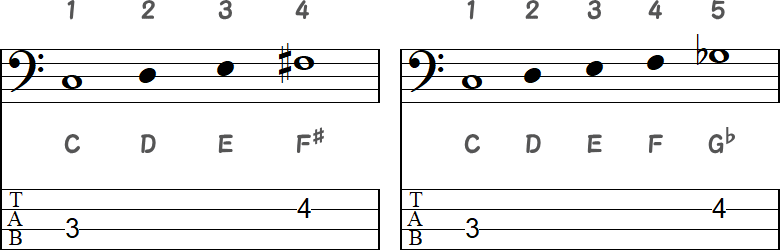
同じ音程でも違う音程
左小節は増4度で、右小節は減5度です。TAB譜だけを見ると同じ音程で、音を聞いても確かに、全く同じ音程です。しかし度数が違うので、増4度と答えるべき問題を、減5度と答えてしまうと、音楽理論的には間違いです。他にもこういった音程は、幾つも存在します。
音程が分かればコードも分かる
ここで説明した事が理解できれば、特にはコードの内容について、分かり易くなると思います。また、度数の種類は他にもあるので、それらについては姉妹サイトの、音程で説明しています。
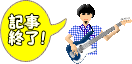
- 先ずはCメジャースケールを1度~8度として考える。
- 度数は始まりの音符を1度として数えていく。
- 度数には長短・完全・増減の冠が付く。