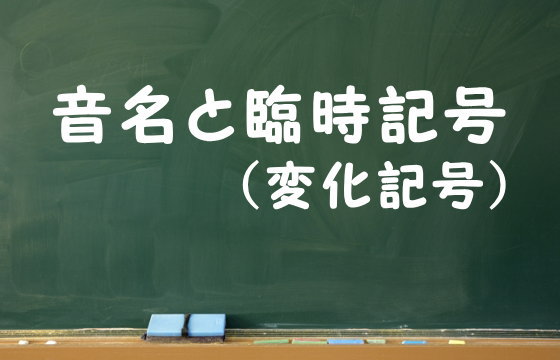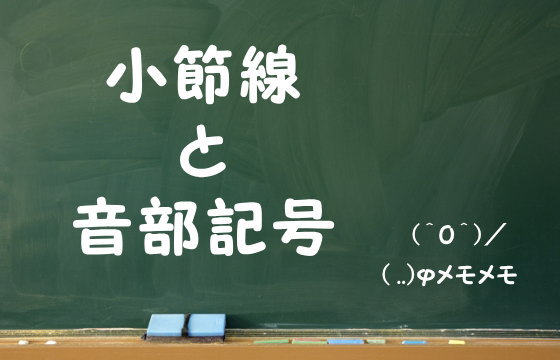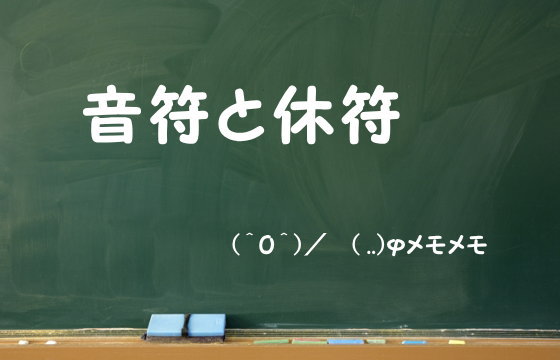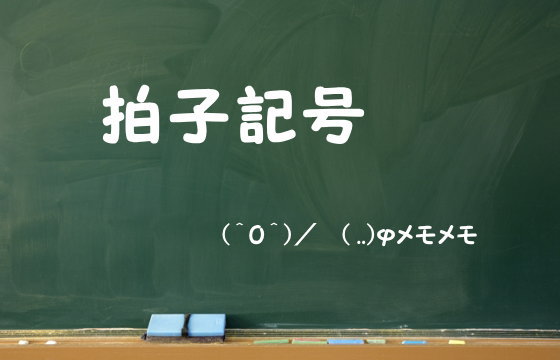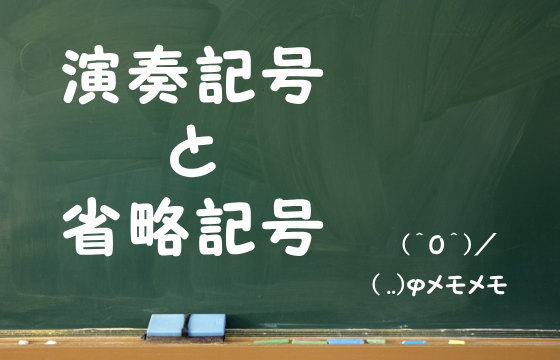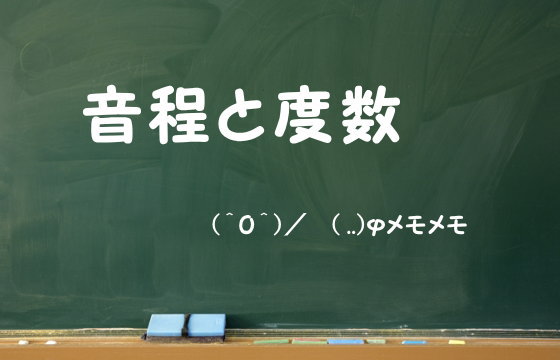譜面は何小節かに渡り、同じフレーズが続く時もあります。そういう場合は、譜面を書く側は手間が省け、譜面を見る側も読み易くなるため、反復記号(はんぷくきごう)を使用する事が多いです。反復記号にも色んな種類がありますが、ここで紹介している代表的なものを、知っておけば良いでしょう。
リピート記号
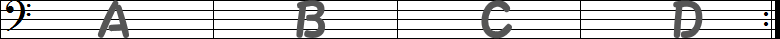
リピート記号の効果
8小節目のHにあるのがリピート記号で、Hを弾き終えたら、再びAへ戻ります。しかし、何度も繰り返す分けではなく、特別な場合を除き、リピート記号の効果は一度きりです。
- 小節の進行順
A⇒B⇒C⇒D⇒E⇒F⇒G⇒H
A⇒B⇒C⇒D⇒E⇒F⇒G⇒H
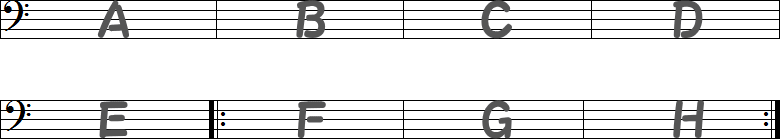
小節を挟んだリピート記号
2小節目のBと7小節目のGを、挟むようにして、リピート記号が位置しています。なので、今度はAには戻らず、Bへ戻り進行していきます。
- 小節の進行順
A⇒B⇒C⇒D⇒E⇒F⇒G
B⇒C⇒D⇒E⇒F⇒G⇒H
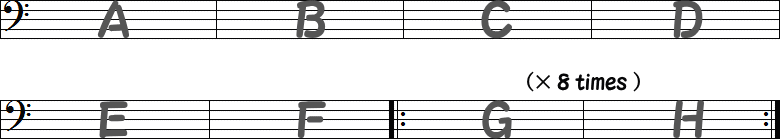
リピートの回数指定
7小節目のGと8小節目のHを、リピート記号が挟んでいますが、今度は(×4 times)という、回数を指定しています。なので、GとHを計4回繰り返します。
- 小節の進行順
A⇒B⇒C⇒D⇒E⇒F⇒G⇒H
G⇒H⇒G⇒H⇒G⇒H
カッコのリピート記号
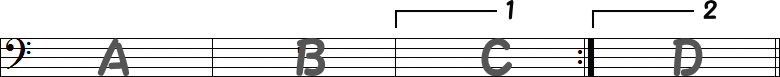
リピート後はカッコ2へ飛ぶ
リピート記号は一緒にカッコを使う事もあります。FのリピートでAへ戻った後、今度はカッコ1のCへは入らず、カッコ2のGへ飛びます。
- 小節の進行順
A⇒B⇒C⇒D⇒E⇒F
A⇒B⇒G⇒H
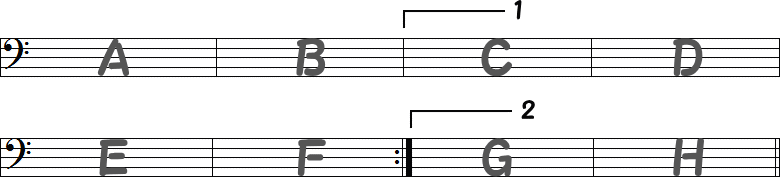
戻る小節と飛ぶ小節
今度は小節を挟んだリピート記号と、カッコ1と2を使った反復記号です。戻る小節と飛ぶ小節に気を付けて、先ずは自分で考えてみましょう。
- 小節の進行順
A⇒B⇒C⇒D⇒E
B⇒C⇒F⇒G⇒H
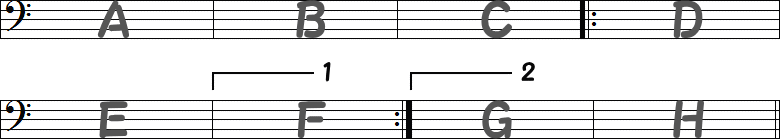
カッコの番号
カッコの番号は1と2だけではなく、3以降も続きます。なので、今度は2回目もCへ入り、3回目でGへ飛びます。この場合のリピート記号は、2回の効果がある分けです。
- 小節の進行順
A⇒B⇒C⇒D⇒E⇒F
A⇒B⇒C⇒D⇒E⇒F
A⇒B⇒G⇒H
ダ・カーポ
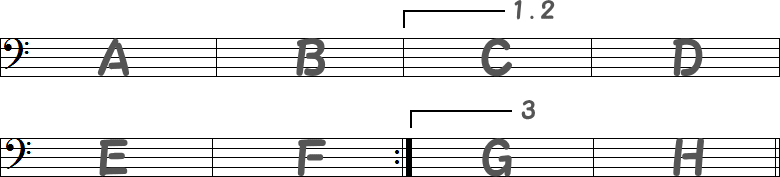
ダ・カーポは最初に戻る
HにあるD.C.(ダ・カーポ)は曲の頭に戻るという意味です。ただ、D.C.は単体で登場する事はなく、次のような記号と一緒に使われます。因みに、D.C.は「Da・Capo」を略したイタリア語です。
- 小節の進行順
A⇒B⇒C⇒D⇒E⇒F⇒G⇒H
A⇒B⇒C⇒D⇒E⇒F⇒G⇒H
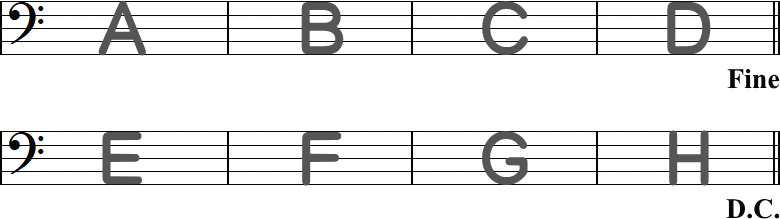
フィーネで終わる
DにあるFine(フィーネ)は終わりという意味です。しかし、1回目のFineは通り過ぎ、D.C.後のFineで終わります。また、Fineと同じく終止を意味する、フェルマータ記号が使われる場合もあります。
- 小節の進行順
A⇒B⇒C⇒D⇒E⇒F⇒G⇒H
A⇒B⇒C⇒D
ダル・セーニョ
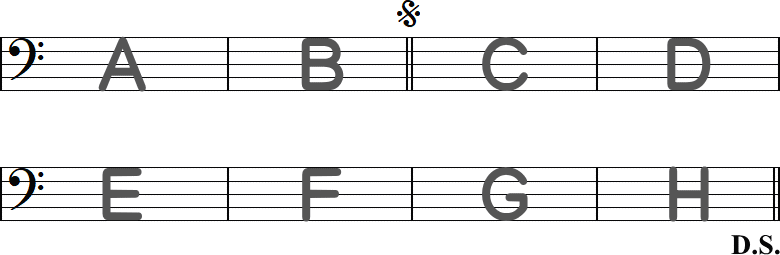
D.S.からセーニョマーク
先ずCにある𝄋(セーニョマーク)が目に付きますが、これは通り過ぎます。HにあるD.S.(ダル・セーニョ)まで来たら、先程の𝄋へ飛びます。因みに、D.S.は「Dal・Segno」を略したイタリア語です。
- 小節の進行順
A⇒B⇒C⇒D⇒E⇒F⇒G⇒H
C⇒D⇒E⇒F⇒G⇒H
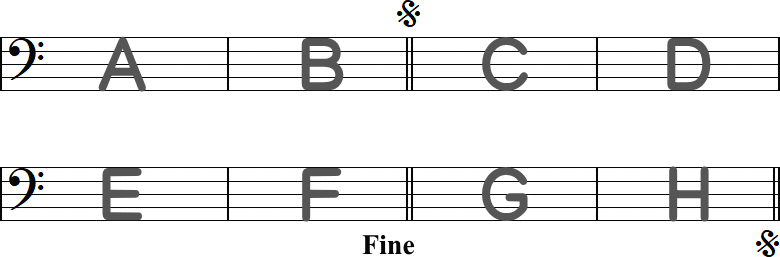
セーニョマークだけ
D.S.の代わりに𝄋が使われる事もあり、その場合は両方とも𝄋になりますが、効果は全く同じです。小節の下にある𝄋から、小節の上にある𝄋へ飛ぶ、と覚えておきましょう。
- 小節の進行順
A⇒B⇒C⇒D⇒E⇒F⇒G⇒H
C⇒D⇒E⇒F
コーダ
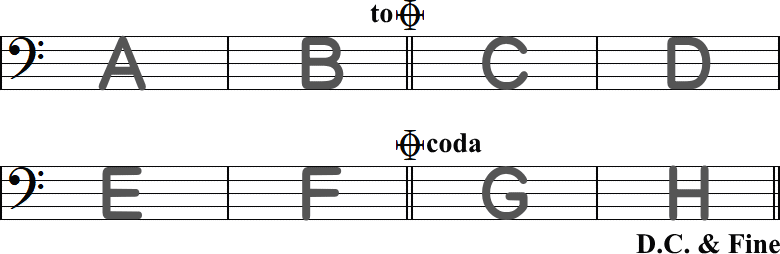
コーダマークも飛ぶ
CとGにある𝄌をコーダマークと言います。先ず両方のto𝄌と𝄌codaは通り過ぎ、D.C.で曲頭へ戻ります。2回目のBを弾き終えたらGへ飛び、2回目のHはFineで終わりです。
- 小節の進行順
A⇒B⇒C⇒D⇒E⇒F⇒G⇒H
A⇒B⇒G⇒H
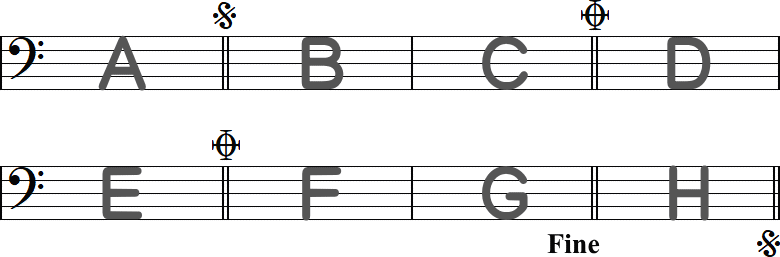
コーダマークだけ
コーダもマークだけが記される時もありますが、toとcodaが省かれているだけです。とは言え慣れていないと、最初は少し戸惑ってしまうかもしれません。
- 小節の進行順
A⇒B⇒C⇒D⇒E⇒F⇒G⇒H
B⇒C⇒F⇒G
ビス・テル・クアテル
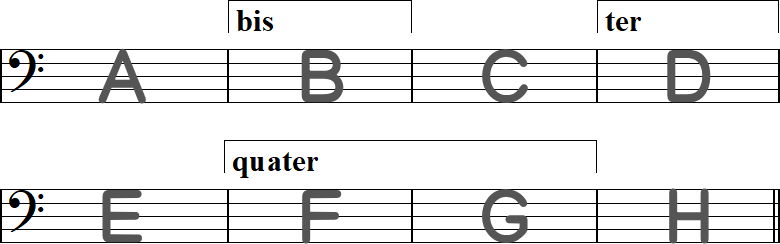
修正用の反復記号
bis(ビス)は2回の繰り返し、ter(テル)は3回の繰り返し、quaterは4回の繰り返しを意味します。これらは完成後の譜面に、修正用として使われるので、市販の譜面では見られないと思います。
- 小節の進行順
A⇒B⇒B⇒C⇒D⇒D⇒D
E⇒F⇒G⇒F⇒G⇒F⇒G⇒F⇒G⇒H
反復記号まとめ
大きな譜面を開く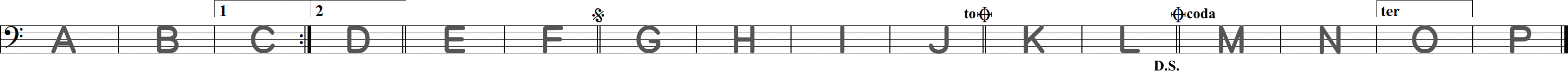
反復記号を見極める
主には直ぐに効果を及ぼす反復記号と、先ずは通り過ぎる反復記号の、二種類に分かれます。それらを見極めれば、どれだけ長い譜面になっても、そう難しいものではないと思います。
- 小節の進行順
A⇒B⇒C⇒A⇒B⇒D
E⇒F⇒G⇒H⇒I⇒J⇒K⇒L
G⇒H⇒I⇒J
M⇒N⇒O⇒O⇒O⇒P
日本語で書いても良い
主に音楽記号はイタリア語で、それが一般的になっていますが、手書きで渡す譜面なら「ここから8小節目に戻る」や「2回繰り返して終わる」という風に、日本語で書いても良いでしょう。実際に私も演奏現場では、日本語で書かれた譜面を、何度も目にした事があります。
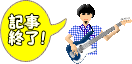
- 先ずはリピート記号を覚える。
- D.S.とCodaはポピュラー音楽でも頻繁に見る。
- D.C.とFineはポピュラー音楽ではあまり見ない。