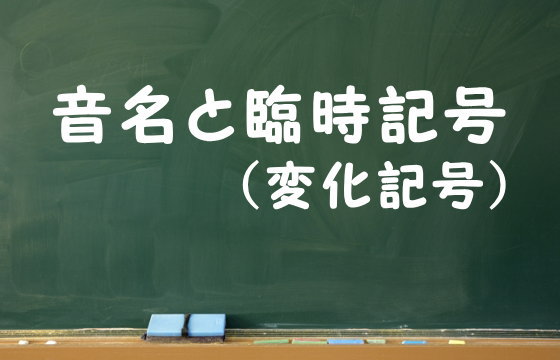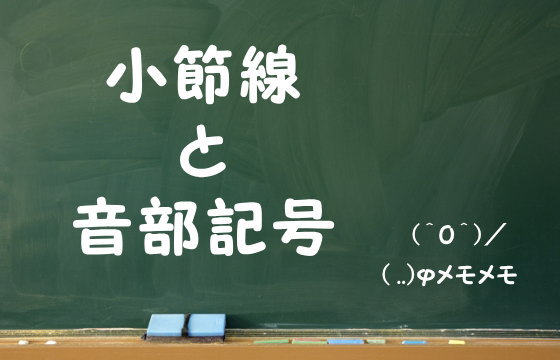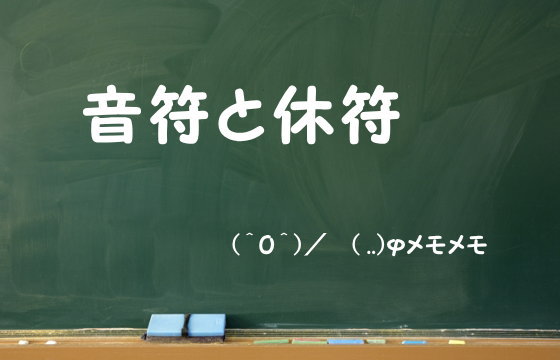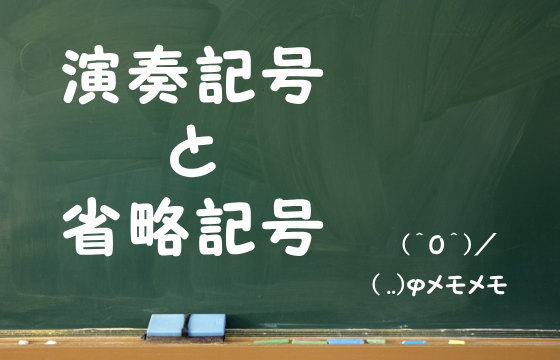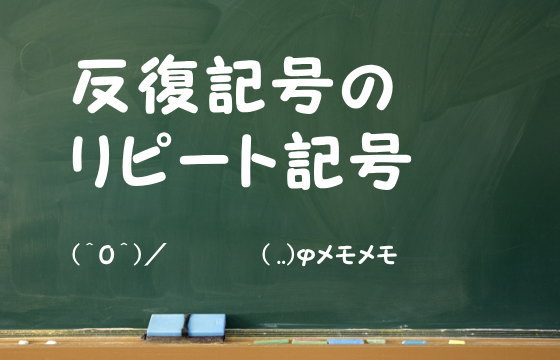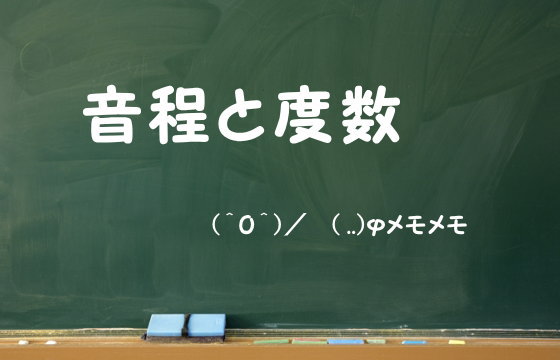譜面の冒頭には分数で表した音楽記号、それを拍子記号(ひょうしきごう)と言います。拍子記号には、どの音符を基準の1拍にするか、それが小節内に幾つ入るのか、という情報を示しています。リズムという言葉は色んな解釈が出来ますが、拍子記号もリズムを決める要素、だと思えば良いでしょう。
拍子記号の計算
-
4分の3拍子(よんぶんのさんびょうし) 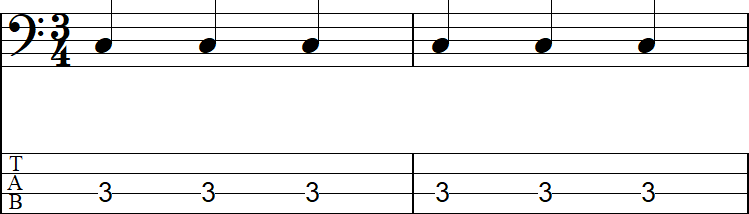
-
4分の4拍子(よんぶんのよんびょうし) 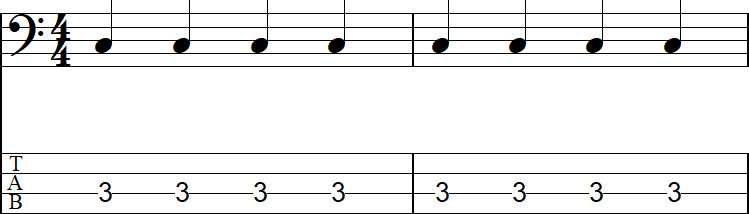
-
2分の3拍子(にぶんのさんびょうし) 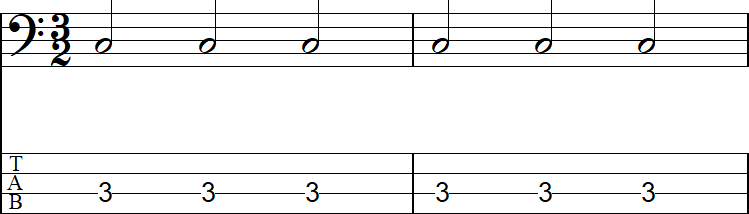
-
8分の6拍子(はちぶんのろくびょうし) 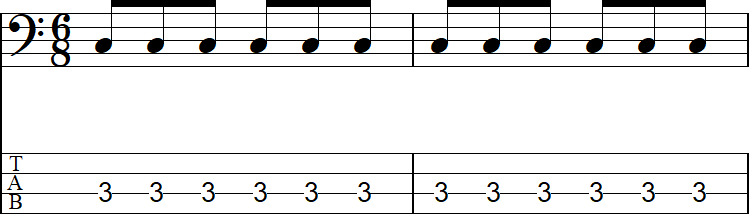
拍子記号で何が変わる?
❶~❹まで音部記号の右隣に、異なる分数が示されていますが、それらが拍子記号です。拍子記号が変わると、基準になる音符の種類や、小節内に入る音符の数が違ってきます。分母と分子の意味を理解してから、❶~❹の拍子記号を考えてみましょう。
- 分子(上)の数字
分母の音符が小節内に入る数を示す。
- 分母(下)の数字
1拍となる基準の音符を示す。
- ❶の
 は分母が4なので、これは4分音符を表しています。分子は3なので、4分音符が3つ入ると、それで小節が終わります。
は分母が4なので、これは4分音符を表しています。分子は3なので、4分音符が3つ入ると、それで小節が終わります。 - ❷の
 は分母が4なので、これも4分音符を表しています。分子は4なので、4分音符が4つ入ると、それで小節が終わります。
は分母が4なので、これも4分音符を表しています。分子は4なので、4分音符が4つ入ると、それで小節が終わります。 - ❸の
 は分母が2なので、これは2分音符を表しています。分子は3なので、2分音符が3つ入ると、それで小節が終わります。
は分母が2なので、これは2分音符を表しています。分子は3なので、2分音符が3つ入ると、それで小節が終わります。 - ❹の
 は分母が8なので、これは8分音符を表しています。分子は6なので、8分音符が6つ入ると、それで小節が終わります。
は分母が8なので、これは8分音符を表しています。分子は6なので、8分音符が6つ入ると、それで小節が終わります。
-
4分の4拍子(ポピュラー音楽の標準) 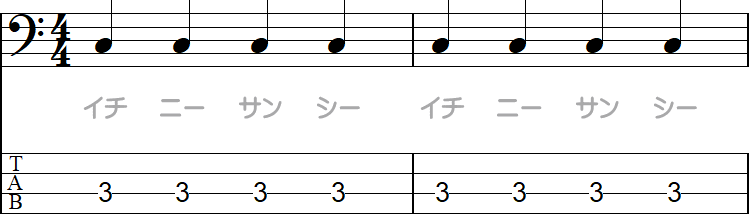
-
4分の3拍子(ワルツ) 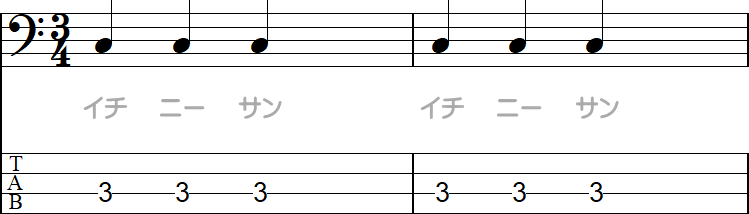
-
4分の2拍子(マーチ) 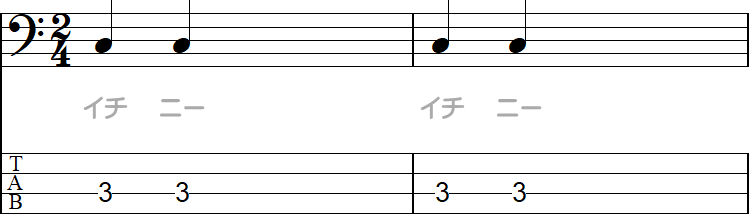
-
4分の1拍子(?) 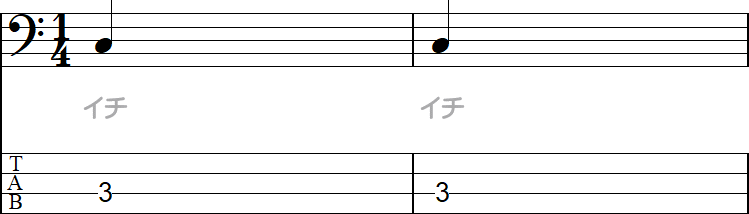
4分の4拍子が標準的
ポピュラー音楽では、❺の「イチ・ニー・サン・シー」で小節を繰り返す、![]() が最も多いです。ワルツと言われる❻の
が最も多いです。ワルツと言われる❻の![]() も多く見られ、マーチと言われる❼の
も多く見られ、マーチと言われる❼の![]() も、そこそこ見られます。❽の
も、そこそこ見られます。❽の![]() の有無は分かりませんが、仮にあったとしたら「イチ」だけで、小節を繰り返す事になります。
の有無は分かりませんが、仮にあったとしたら「イチ」だけで、小節を繰り返す事になります。
-
4分音符の3拍子 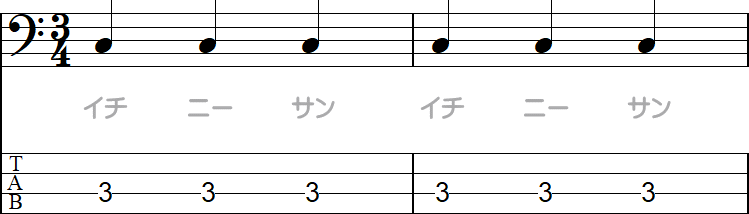
-
2分音符の3拍子 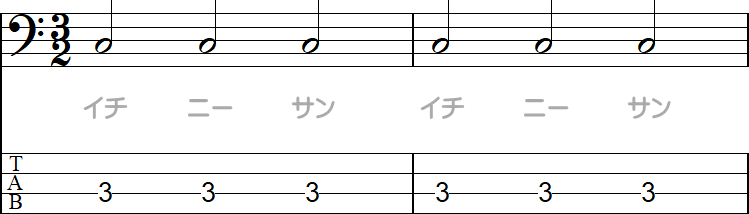
-
8分音符の3拍子 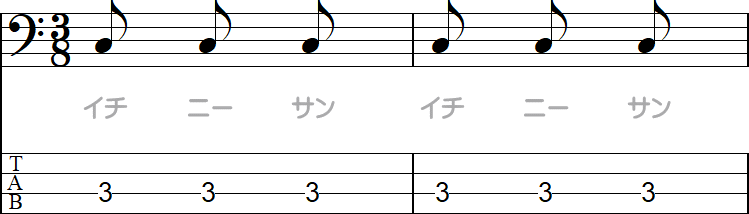
1拍となる音符は変わる
分母は1拍となる音符ですが、❾の4分音符がリズムを取り易いでしょう。しかし、❿の2分音符になったり、⓫の8分音符になったりもします。これは曲調によって使い分けられ、例えば、ゆったりした曲なら2分音符、軽快な曲なら8分音符、と言った具合です。
-
4分音符が3つだけ4分の3拍子 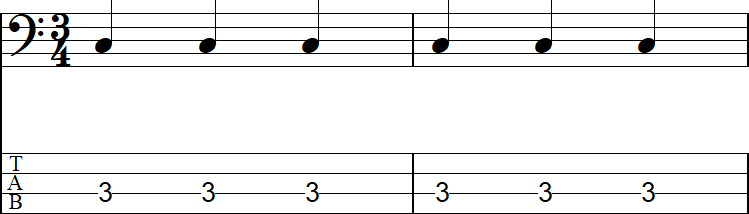
-
4分音符以外もある4分の3拍子 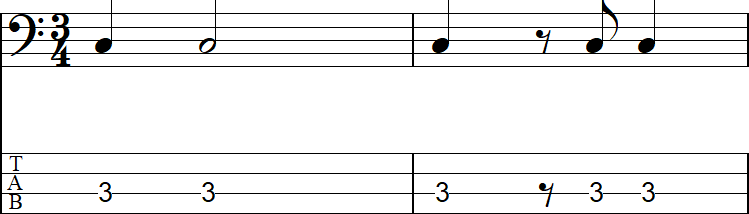
符割の計算も必要
⓬は![]() で1・2小節目ともに、4分音符が3つずつ入っており、分かり易いです。しかし当然⓭のように、他の音符や休符も入ってきます。なので、小節内が4分音符3つ分になっているか、自分で確かめてやる必要も出てきます。こういった事を「符割(ふわり)を確かめる」等と言います。
で1・2小節目ともに、4分音符が3つずつ入っており、分かり易いです。しかし当然⓭のように、他の音符や休符も入ってきます。なので、小節内が4分音符3つ分になっているか、自分で確かめてやる必要も出てきます。こういった事を「符割(ふわり)を確かめる」等と言います。
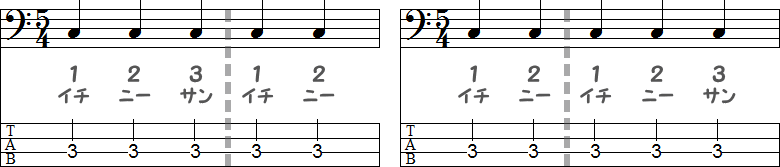
拍子記号は曲中で変わる
拍子記号は曲中に変わる事もあります。上記はポピュラー音楽でもよくある例で、![]() で開始した曲を、ある小節だけ
で開始した曲を、ある小節だけ![]() に変えています。そういった場合は、拍子記号が変わる前の小節を、複縦線にしておくと分かり易いです。
に変えています。そういった場合は、拍子記号が変わる前の小節を、複縦線にしておくと分かり易いです。
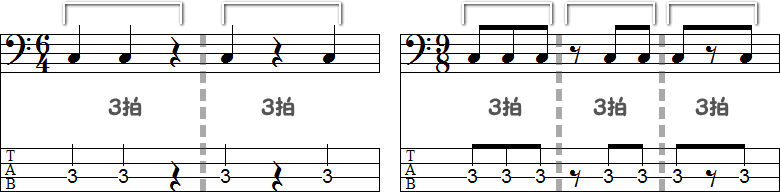
拍子記号の略記号
左小節の![]() は
は![]() の略記号で、非常によく使われます。これはアルファベットのCではなく、大昔の譜面の書き方で使用されていた、定量記譜法(ていりょうきふほう)、というものの名残だそうです。右小節の
の略記号で、非常によく使われます。これはアルファベットのCではなく、大昔の譜面の書き方で使用されていた、定量記譜法(ていりょうきふほう)、というものの名残だそうです。右小節の![]() は
は![]() の略記号で、これもよく使われます。
の略記号で、これもよく使われます。
拍子記号の強拍や弱拍
拍子記号が変わると、強拍(きょうはく)や、弱拍(じゃくはく)という、どの拍を意識して重く感じたり、軽く感じたりするのか、も違ってきたりします。それは姉妹サイトの、拍子記号で説明しています。
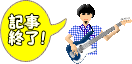
- 拍子記号の分子は、基準の音符が入る数。
- 拍子記号の分母は、1拍となる基準の音符。
- 拍子記号は略記号もあり、頻繁に使われる。