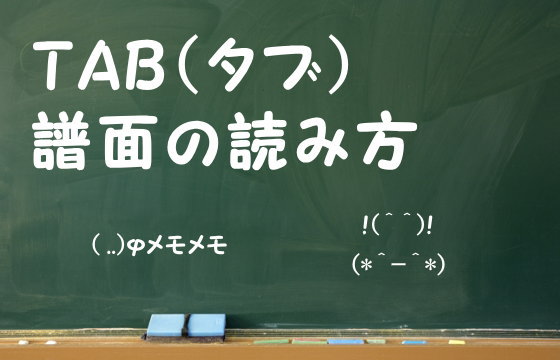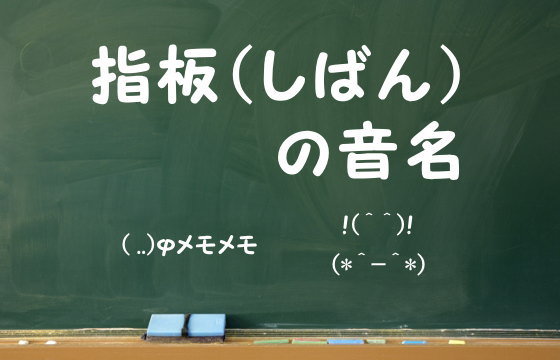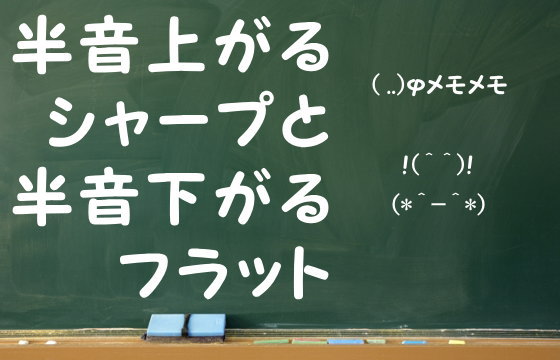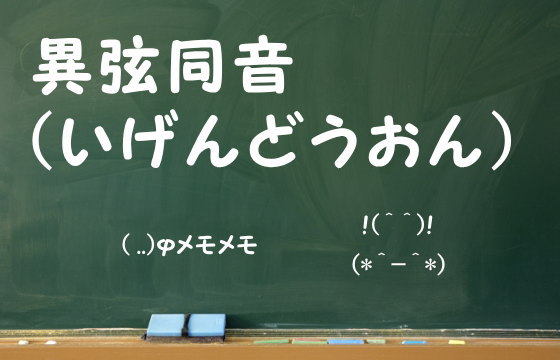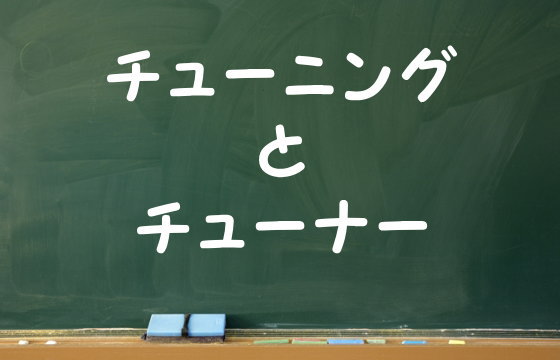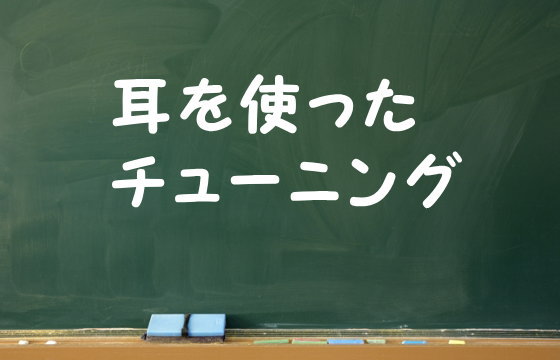弦を押さえる場所は「座標」のような感じになっています。それを数字・弦・フレットを合わせ、表現するのがフレットの見方で、タブ譜面を読む事に直結しています。実物のエレキベースを画像化した指板、というのも多く使われているので、それにも慣れておきましょう。
弦とフレット
-
指板図 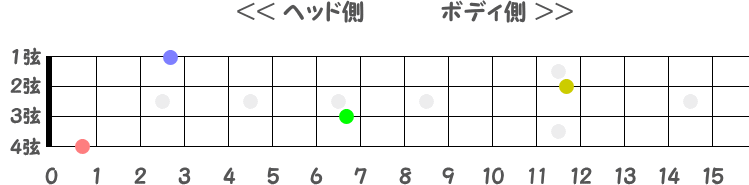
-
指板図(左利き用) 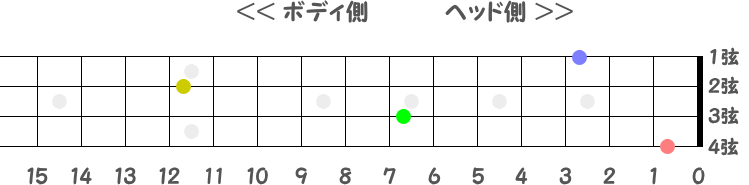
指板を簡略化した画像
ベースの教則本などでは、指板を簡略化した画像を使い、どの音を押さえて弾くかを、表したものがよく使用されます。ここではそれを指板図(しばんず)と称して、説明しています。上記の指板図にも見られる「●・●・●・●」の、読み方を考えていきます。
左利き用の指板図
左利き用のベースを使用されている方は、❷の指板図が分かり易いですが、以下では❶の右利き用で説明しているので、所々で注意が必要です。
弦の見方
指板図の横線は弦を表し、下から4弦・3弦・2弦・1弦という並びです。それぞれ●は4弦の上、●は1弦の上、●は3弦の上、●は2弦の上、にあるのが分かります。
フレットの見方
指板図の縦線はフレットを表し、番号が振ってある通り、左から順に1・2・3フレットと数えます。なので●は1フレット、●は3フレット、●は7フレット、●は12フレット、に位置しているのが分かります。
-
エレキベース 
-
エレキベース(左利き用) 
エレキベースの画像で確認
先程の「●・●・●・●」を実際のベースに置いてみると、上記のような感じになります。指板側を仰向けにして、ヘッド側を左にして寝かせてやると、指板図と同じ見方が出来るわけです。弦とフレットの数え方は分かったと思うので、これらの位置を表現してみます。
- ● - 4弦1フレット
- ● - 1弦3フレット
- ● - 3弦7フレット
- ● - 2弦12フレット
◯弦◯フレット
上記のように、何処を押さえて弾くかは◯弦◯フレットという感じで表します。最初は何フレットか迷う事も多いので、そういう場合は、ポジションマークを利用してやりましょう。
上下が逆になる
指板図では、最も細い1弦が一番上になり、最も太い4弦が一番下、という見方になります。しかし、実際にベースを持って構えると、1弦が一番下になり、4弦が一番上になります。
押弦・運指・開放弦
-
3弦3フレット 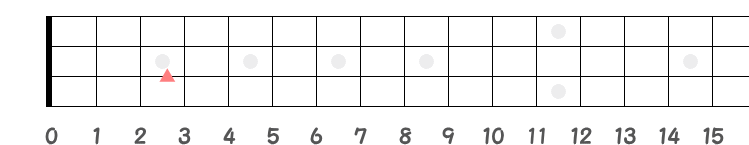
-
3弦3フレット(左利き用) 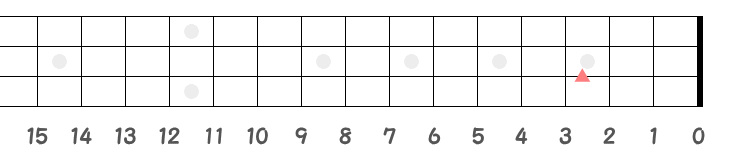
押弦とは?
上記の指板図では▲が3弦上にあり、3フレット目にあるので、3弦3フレットを押さえる、という意味です。この弦を押さえる事を、専門用語で押弦(おうげん)と言うので、覚えておきましょう。
-
1弦1フレット 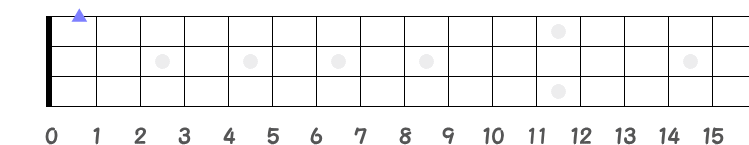
-
1弦1フレット(左利き用) 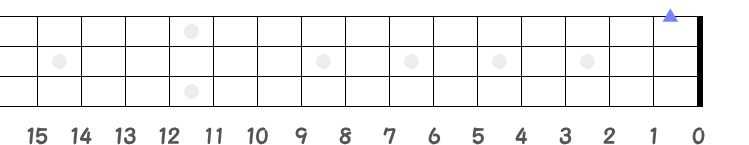
運指とは?
次の指板図では▲が1弦上にあり、1フレット目にあるので、1弦1フレットを押弦します。押弦の他にも運指(うんし)するとも言いますが、運指は正確に左右両手の指使い、の事を言います。
-
2弦0フレット 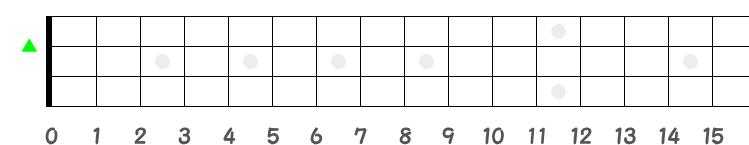
-
2弦0フレット(左利き用) 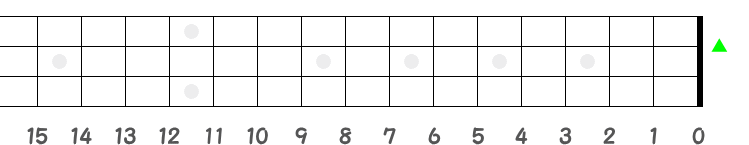
開放弦とは?
今度の▲は2弦にあるようですが、弦上にはないので、押弦せずに弾く事を意味します。これは2弦0フレットですが、0フレットの事を開放弦(かいほうげん)とも言います。
-
4弦0フレット 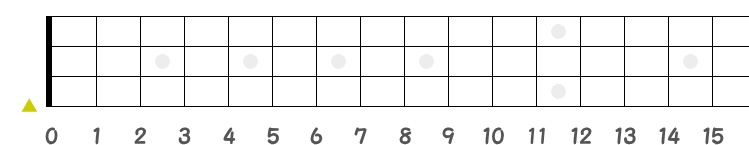
-
4弦0フレット(左利き用) 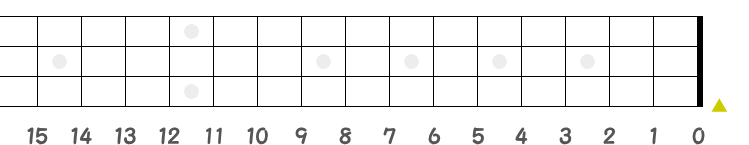
4弦の開放が最低音
最後の▲は4弦0フレット、または4弦の開放です。通常の4弦ベースでは、これが最低音になるので、覚えておきましょう。
指板図とベース指板は違う
実物のエレキベースでは、4本の弦の太さはそれぞれ違い、フレットの幅も違いますが、このサイトで扱う指板図は、全て均等になっているので、注意してください。
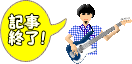
- 指板図の横線は弦で、縦線はフレットを表す。
- 弦を押さえる事を押弦や運指と言う。
- 開放弦は0フレットのこと。