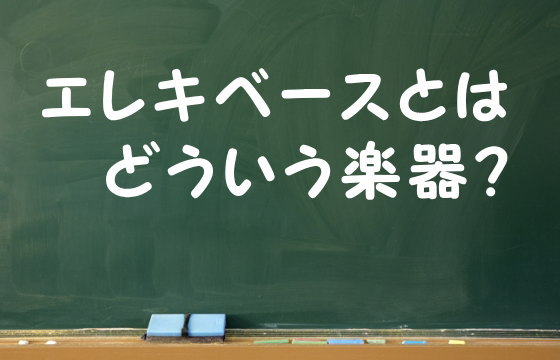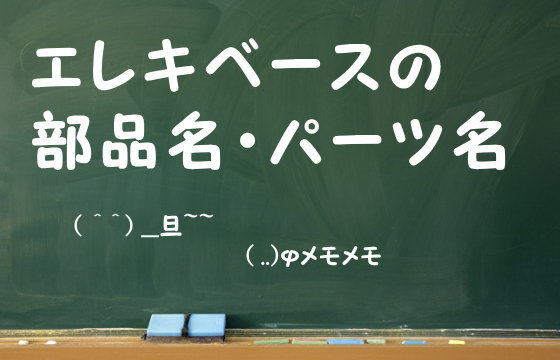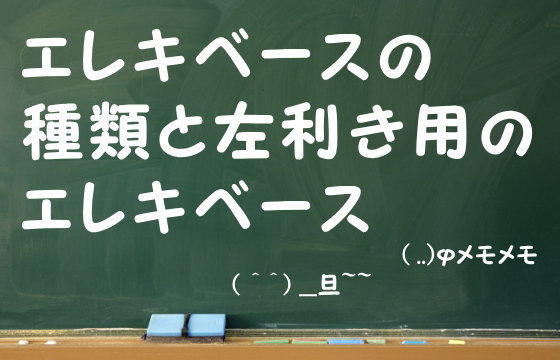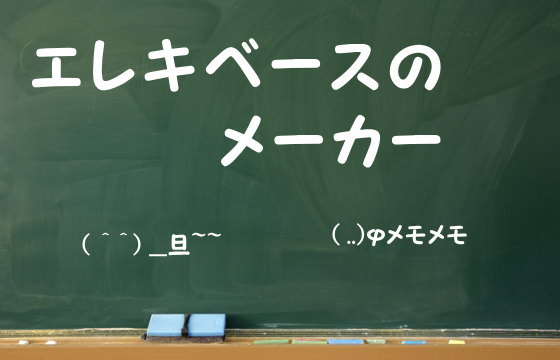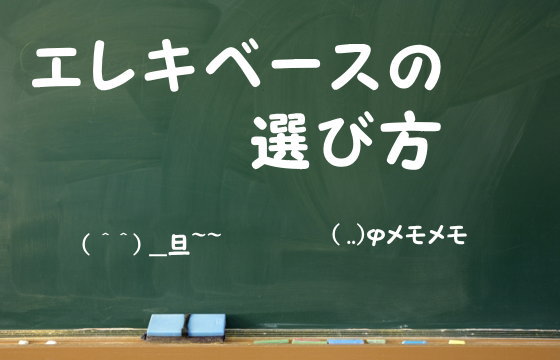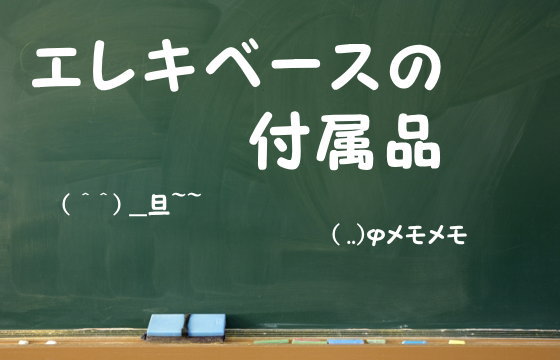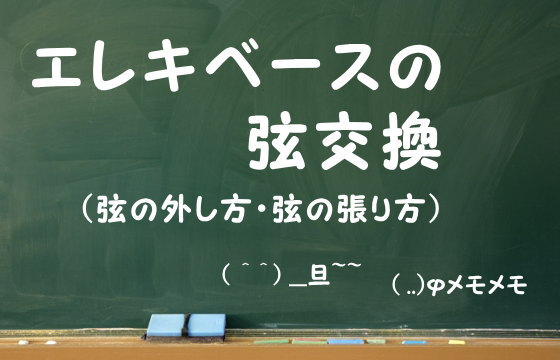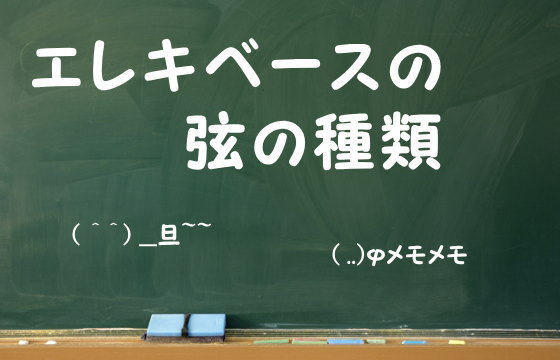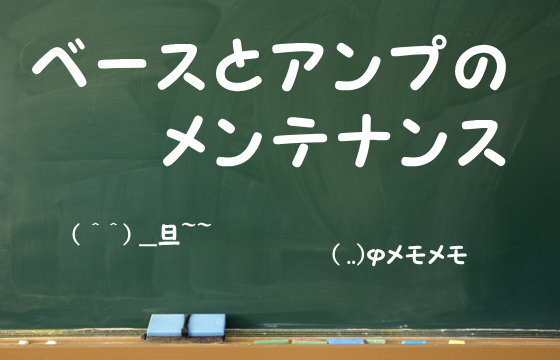ベースの音は主にベースアンプにある、ツマミを回したり、上げ下げしたりして変えます。それらツマミの数は、ベースアンプによって違いますが、ここでは基本的なツマミの名前と、どういった音になるのかを説明します。また、自宅用とライブ用のベースアンプの違いも、知っておきましょう。
基本のEQとフラット
基本のEQを知る
アンプのツマミには色んな種類があり、それぞれ音色も違いますが、それらをまとめてEQ(イコライザー)と言います。基本的なEQは三種類なので、先ずはそれらの名称を覚えておきましょう。
- BASS(ベース)は低音域
エレキベースでは主役みたいな音で、太さや分厚さの低音を作り、バンド全体を支えます。しかし、低音を上げ過ぎてしまうと、モワモワして聞き取り辛い音になってしまいます。
- MIDDLE(ミドル)は中音域
抜けの良い音や、芯の通った音が欲しい場合には、ミドルの調節が重要になってきます。これも上げ過ぎると、ぼやけてモコモコした感じになるので、気をつけましょう。
- TREBLE(トレブル)は高音域
元気の良い張りのある音が作れますが、やはり上げ過ぎてしまうと、耳障りな音になってしまいます。弦がフレットに当たるビビリの時にも、邪魔な音になってしまいます。
- PRESENCE(プレゼンス)は超高音域
高音域の部類に入りますが、更に上の超高音域と呼ばれ、特にはスラップ奏法の時に、設定に気を遣うかもしれません。上げ過ぎはノイズの原因になります。
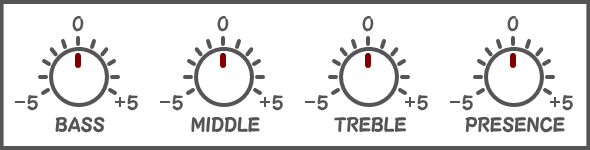
音作りはフラットから
上記の画像はツマミのメモリを、プラスにもマイナスにもせず、0に合わせてあります。この初期状態のような感じをフラットと言い、音作りはフラットから始める、というのがポイントです。フラットになっている時が、そのベースアンプの標準的な音と言えます。
スタジオアンプのマナー
自宅用のベースアンプもそうですが、特に練習スタジオでアンプを使い終わった時は、EQをフラットの状態(または最小の0)、ボリューム等も0にして帰りましょう。
ブーストとカット
アンプで音を作る時に、ツマミを上げて音を足す事をブースト、ツマミを下げて音を引く事をカットと言います。この後にも説明していますが、ブーストとカットを上手に使い分けられるかで、ベースアンプの音作りは大きく左右されます。
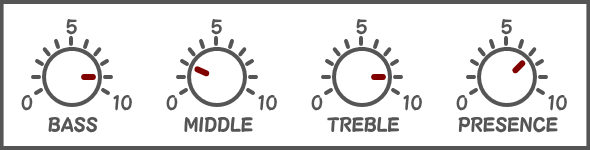
ドンシャリはMIDDLEを低め
BASSとTREBLEをブーストして、MIDDLEをカットすると、低音がドンドンと力強く、高音がシャリシャリと目立ちます。この設定を俗にドンシャリと言い、特にはスラップベーシストに好まれる音です。しかし、音が埋もれてしまう傾向もあり、聞き取り辛くもなるので、気を付けましょう。
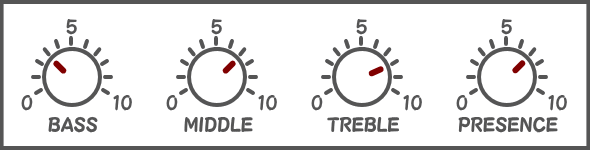
抜けの良い音はBASSを低め
MIDDLEとTREBLEをブーストして、BASSをカットすると、張りのある抜けの良い音が作れます。BASSをカットしているので、音圧は感じられず細い音ですが、バンド全体でも聞き取り易い音、というのが期待できます。デメリットはノイズが大きめ、という事でしょうか。
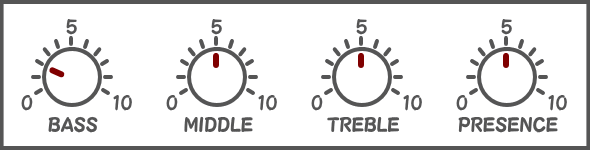
カットのみでも音は作れる
フラットの状態からブーストはせず、カットのみで作った抜けの良いEQです。このように、ブーストよりもカット中心の音作りは、ベテランベーシストによく見られる傾向です。バンド全体を通した時に、足りないEQがあれば、ブーストしていくと良いでしょう。
ブーストの注意点
ブースト中心の音作りは、あれもこれも音を足してしまい、結局は音量だけが上がってしまう、という事もよくあります。要らない音をカットしていく、上手い音作りも覚えておきましょう。
グライコとパライコ
グライコの周波数
上下に動かすツマミをグライコ(グラフィックイコライザー)と言い、以下に記しているHz(ヘルツ)や、KHz(キロヘルツ)の周波数単位で、低音域・中音域・高音域を設定します。それらはベースアンプによって数も違い、多ければ細かな設定が出来ますが、それだけ迷うという事もあります。
- BASS(低音域) - 50Hz辺り~400Hz辺り
- MIDDLE(中音域) - 400Hz辺り~4.5KHz辺り
- TREBLE(高音域) - 4.5KHz辺り~10KHz辺り
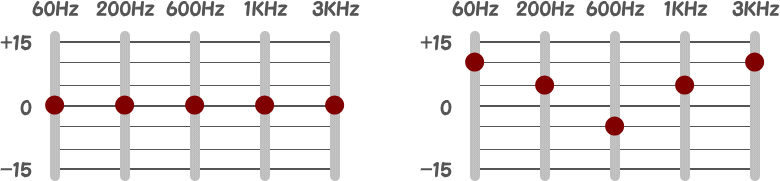
グライコは左側から低音域
周波数の数値を覚えなくても、グライコは左側が低音域で、右側へ行くにつれ高音域、と覚えておけば良いでしょう。上記のグライコなら、左はツマミが全て0なのでフラット、右は低音と高音がブーストし、中音をカットしているので、ドンシャリ系と言えるでしょう。
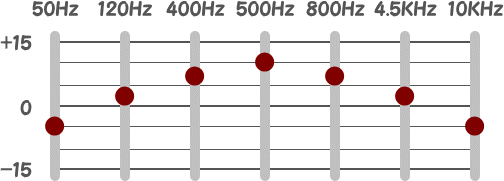
グライコの見た目がカマボコ
今度のグライコはツマミが7つあり、低音域から少しずつ上がり、中音域の500Hzを頂点とし、高音域にかけて下がっています。このツマミの見た目からカマボコと言われ、モコモコとした音が特徴です。主にはピック弾きベーシストに、しばしば好まれる設定のようです。
グライコの良し悪し
その見た目からグライコは、直感的に欲しい音が作り易いです。しかし、周波数の幅が決められており、物足りなさを感じるようになります。また、ツマミの数に比例し、ノイズも大きくなります。
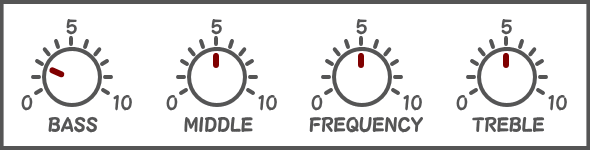
パライコも周波数を変える
グライコと双璧をなすのがパライコ(パラメトリックイコライザー)です。パライコも周波数を操り、グライコより細かな設定が可能ですが、その分だけ複雑で、慣れるのに時間を要します。
FREQUENCYは周波数
パライコの1つにFREQUENCY(フリーケンシー)というEQがあり、周波数を意味します。例を挙げると、先ずは通常と同じく、BASS・MIDDLE・TREBLE・PRESENCEで音を作ります。更にそれぞれに応じたFREQUENCYがあるので、細かな設定を作り上げられる、という具合です。
パライコの良し悪し
FREQUENCYだけを例に挙げましたが、パライコは他にも数種類のEQがあり、使いこなせるまでが大変です。しかし、音作りの幅はグライコより自由です。
GAINとアンプの種類
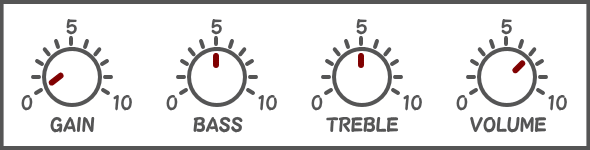
GAINは歪みを作れる
GAIN(ゲイン)はギタリストには馴染み深い、ギュイ~ンというような、歪(ひず)みを作るEQです。ベースアンプのGAINでは、エレキギター並みの歪みは作れませんが、ドライブ感のある元気な音が出せます。ただ、GAINを上げると全体の音量も上がるので、VOLUME(ボリューム)で調整が必要です。
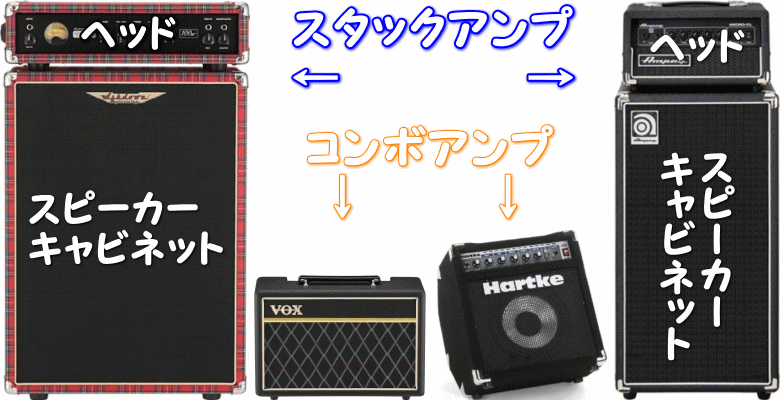
GAINはスタックアンプ
ヘッド(ツマミを調節する部分)と、スピーカーキャビネットが分かれたものを、スタックアンプと言います。ヘッドには大抵GAINが備えられていますが、自宅練習用に多いコンボアンプには、ほとんどGAINは装備されていません。しかし、エフェクター(オーバードライブetc.)を使えば、GAIN感は出せます。
ベースアンプも慣れが必要
ライブハウス等により、当然ベースアンプは違ってくるので、欲しい音を作るのに苦労します。やはりベースアンプの音作りも、慣れや経験が必要でしょう。
ベースアンプの接続
故障の原因になる
最後にベースとアンプの、接続手順を確認しておきましょう。慣れてしまうと、スイッチがオンの状態でシールドを抜き差ししたりと、いい加減になる人も多いです。故障の原因にもなりやすいので、無駄な修理代も掛かり、良い事はありません。また、水分を近くに置くのも避けましょう。
- ベースとアンプの音量を全て0にする。
- 最初にベースにシールドを差し込む。
- 次にアンプにシールドを差し込む。
- アンプのスイッチを入れる。
- 演奏後は音量を全て0にしてスイッチを切る。
- 直ぐにシールドを抜かない。
なるべくアンプを通して練習
ベースアンプを通して練習すると、自分の意図としていない音が鳴っている、という事に気づき易いです。なので、なるべくはベースアンプを使った練習、というのをお勧めします。
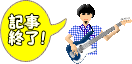
- ベースアンプの音作りはフラットから。
- グライコは分かり易く、パライコは音色の幅が広い。
- スタックアンプにはGAINもある。