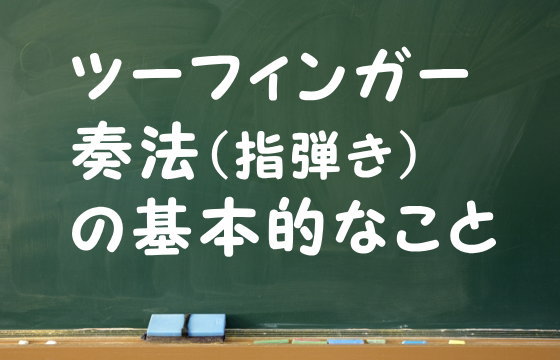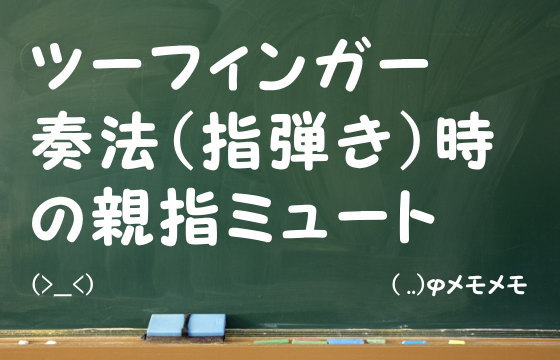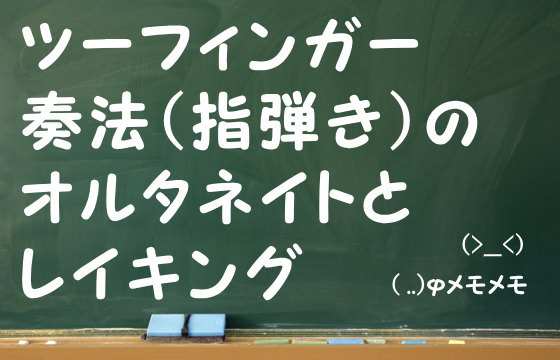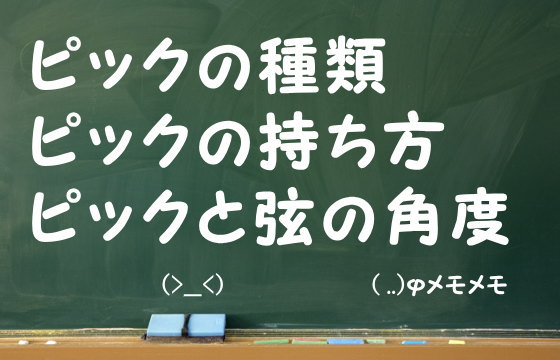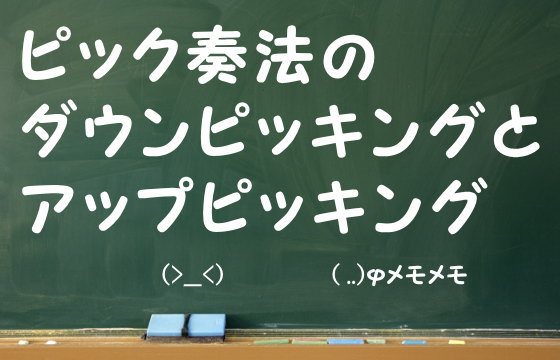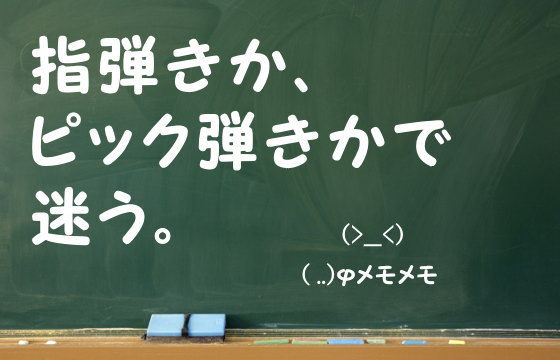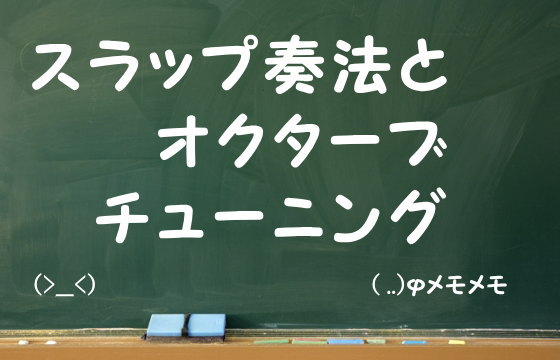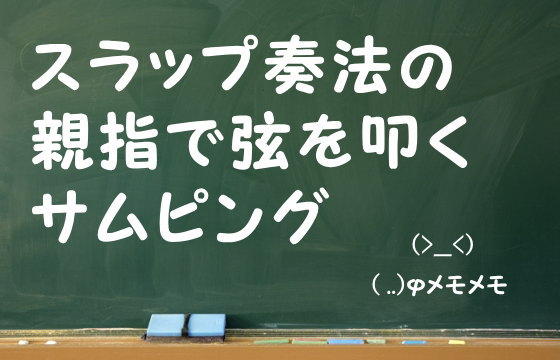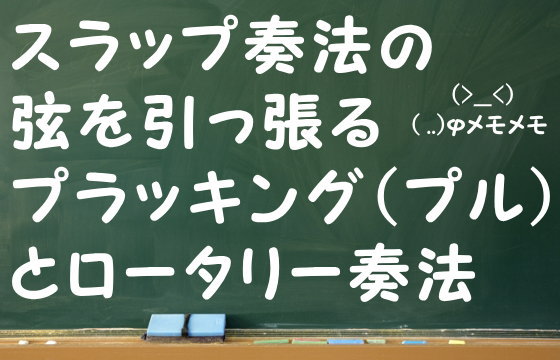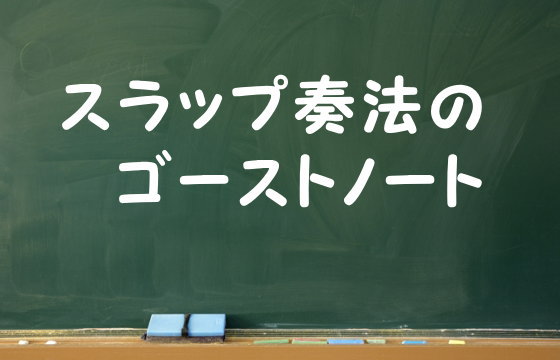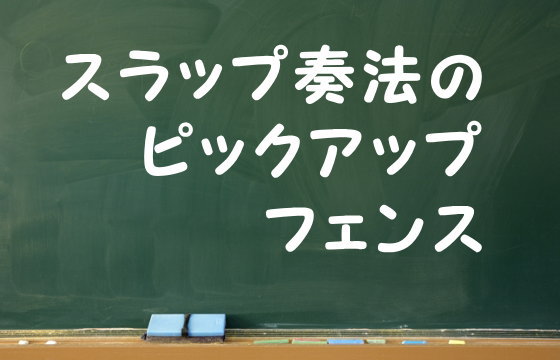ピック奏法は肘を始点とする弾き方と、手首を始点とする弾き方に、分けられる事が多いです。これらの両方は、自身の演奏スタイルによって、使い分けると良いでしょう。また、音を止めるミュートと、音を鳴らすミュート奏法、という事についても知っておきましょう。
ピック奏法の始点
肘が始点のピック奏法
肘からは力強い音
肘の動きを使う場合は、肘から下を固定させますが、腕をガチガチにさせてしまうのは、よくありません。リラックスさせながらも、腕の力を利用して、弾き下ろす、弾き上げる、といった感じでしょう。肘からのピック奏法は、腕全体を使って弾くので、慣れれば楽に、力強い音を出せるでしょう。
手首が始点のピック奏法
手首からは速弾き
手首の動きを使う場合は、手首周辺をボディに置き、軽く固定させてやると、良いかもしれません。やはり手首に力を入れ過ぎるのではなく、団扇を扇ぐような感覚で、弾ければバッチリです。手首からのピック奏法は、細かいフレーズや、速弾きに適しているでしょう。
大きな譜面を開く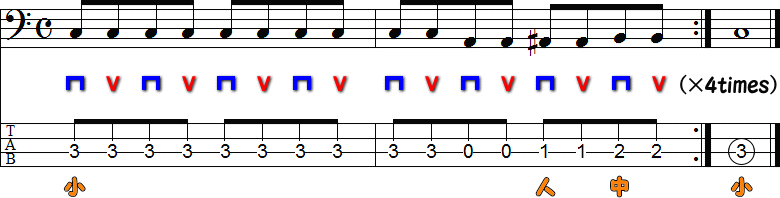
ストラップの長さ
動画でも見たように、肘と手首の始点を意識し、弾いてみましょう。肘からのピック奏法ですが、座って弾くのはもちろん、立って弾く時のストラップが短めでも、腕が窮屈になり弾き辛いです。ピック弾きベーシストの多くは、音楽スタイル的に、ストラップが長めの場合が多いでしょう。
座奏と立奏
音楽用語で座って演奏する事を座奏(ざそう)、立って演奏する事を立奏(りっそう)と言います。
ピック奏法のミュート
音を鳴らすミュート奏法
パームミュートで曇った音
ピックを摘まみつつ、チョップ部分をブリッジ付近の、弦に触れさせておきます。その状態で弾いてやると、曇った短い音が出せます。これがピックのミュート奏法の一種で、パームミュート等と言われます。因みに、パームは手の平を意味し、ピックの代わりに親指を使う、パームミュートもあります。
音を止めるミュート
音を完全に切るミュート
鳴っている音を止めるには、弦をフレットから離せば良いのですが、残響音が出てしまう事もあります。音を完全に切りたい場合は、先程のパームミュートに似たフォームで、音を止める方法があります。これがピック奏法でよく使われる、ミュートの一つです。
チョップミュート(仮)
二通りのミュートを説明しましたが、次からやっていくことは、音を止めるミュートの方です。しかし、ミュートさせる弦はありながらも、違う弦はピックで弾き音を出す、という難しいフィンガリングです。以下ではそれを、パームミュートと区別して、チョップミュートとして、説明していきます。
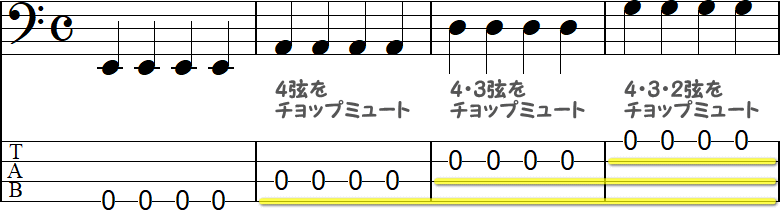
チョップミュートは共鳴防止
共鳴というのは、鳴っている弦の振動に釣られ、他の弦も震えだし、音が鳴ってしまう現象です。これをピック奏法では、チョップミュートで防止していきます。上記の4小節を例に挙げ、チョップミュートを練習してみましょう。
- 1小節目
チョップミュートの必要はありません。しかし、1・2・3弦が4弦の振動で共鳴するので、それは押弦する方の手を、1・2・3弦に触れさせ、ミュートしておきましょう。
- 2小節目
4弦をチョップミュートします。それでいて、3弦を弾かなければならないので、器用なスキルを必要とします。1・2弦は押弦の手でミュートです。
- 3小節目
4・3弦をチョップミュートします。2弦までもチョップで触れてしまわないよう、絶妙な位置を見つけましょう。1弦は押弦の手でミュートです。
- 4小節目
4・3・2弦をチョップミュートします。チョップミュートの範囲が広いので、最も難しいフィンガリングになるかもしれません。
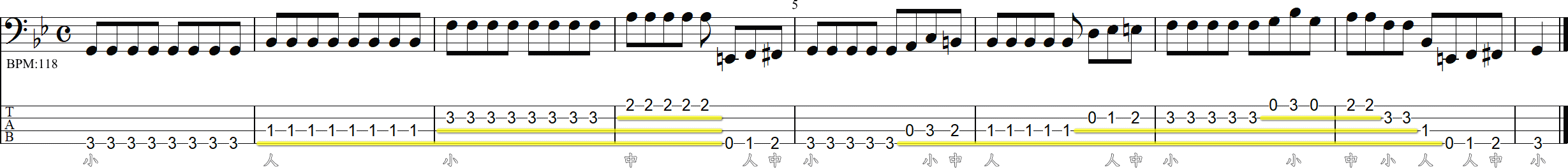
チョップミュートは焦らず
今度は実践風で、チョップミュートを練習してみましょう。かなり難しいですが、共鳴は直ぐに起こる現象ではないので、例えば2小節目なら、3弦1フレットを弾くと同時に、4弦をチョップミュートする必要はありません。弾きながらも、チョップミュート出来るフィンガリングを、見つけていきましょう。
チョップミュートの必要性
一概には言えませんが、ピック弾きならロックやパンクなど、賑やかなジャンルが多いので、共鳴など気にならないベーシストもいます。チョップミュートも、必要に応じて使いましょう。
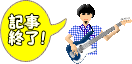
- ピック奏法の始点は、肘と手首に分けられる事が多い。
- 斜めのオルタネイトピッキングで、ピックが弦を抜け易くなるかも。
- ピック奏法にも共鳴を防ぎながら、弾くチョップミュートがある。