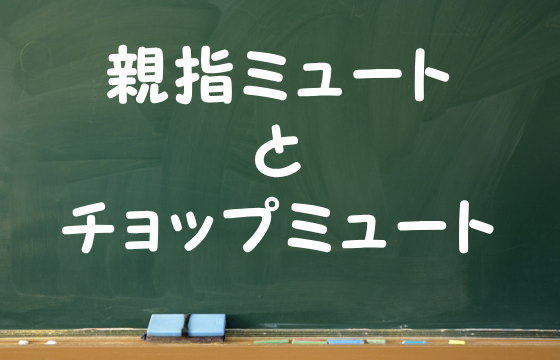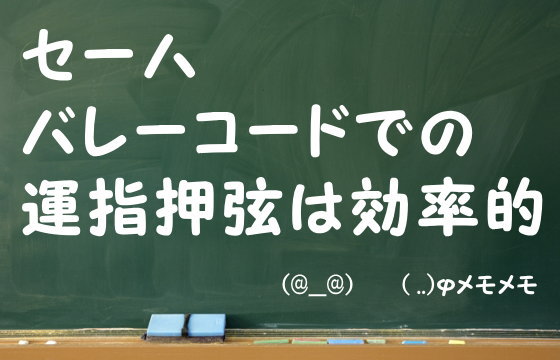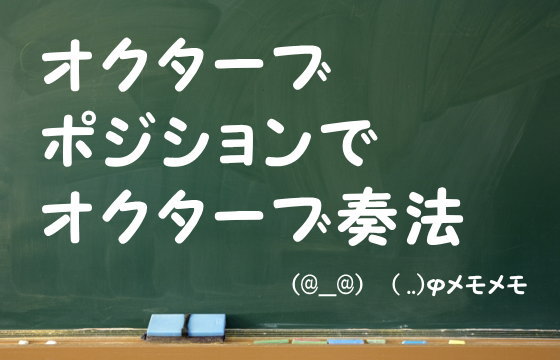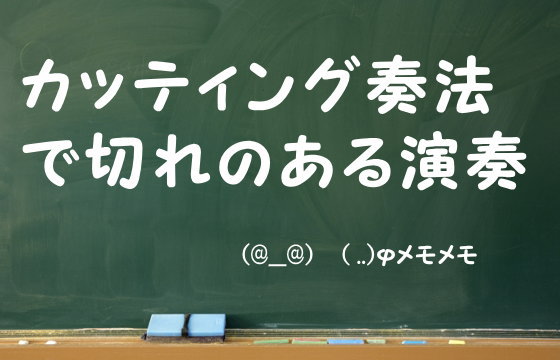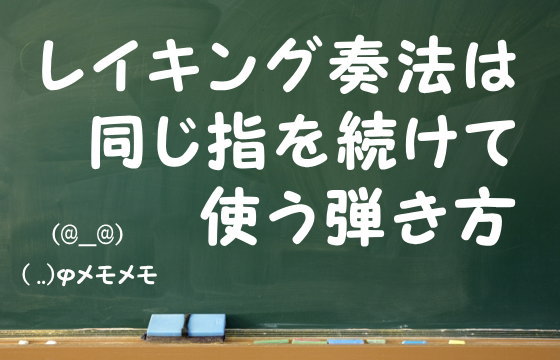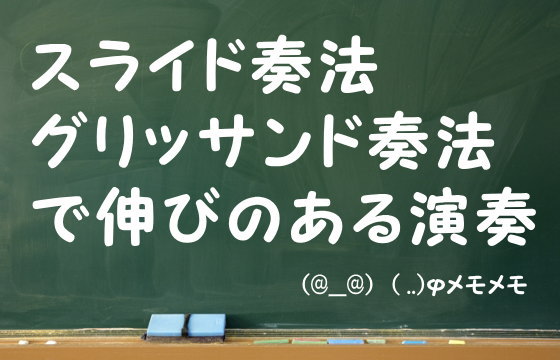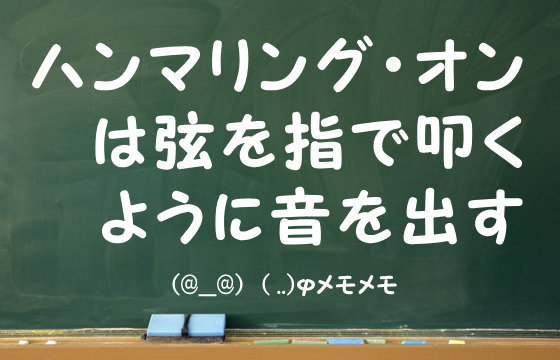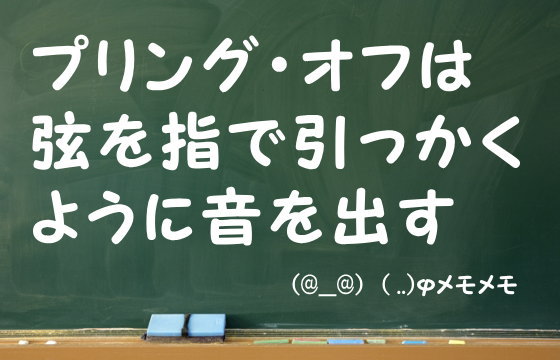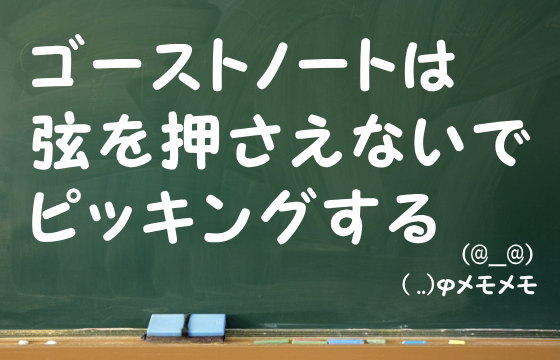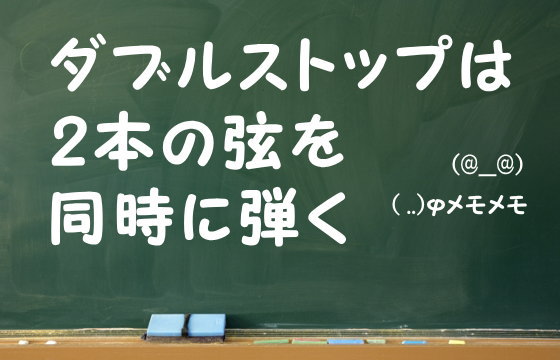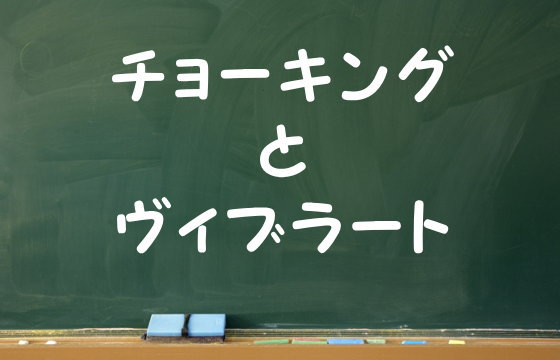一定の音を刻む事を英語ではビート、日本語では拍(はく)と言われます。小節に並ぶ音符にはそれぞれ、種類の違う拍が振り分けられており、それらを強拍(きょうはく)・中強拍(ちゅうきょうはく)・弱拍(じゃくはく)、と言います。先ずはこれらの拍について、基本的な事を見ていきましょう。
強拍・中強拍・弱拍
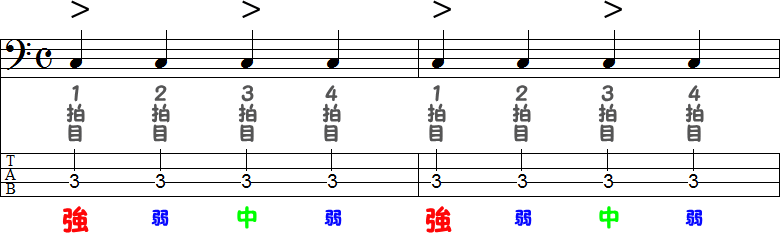
4分音符と拍
最も分かり易い例えですが、小節内に4分音符が4つ並んだとします。そうした時、1つ目を1拍目、2つ目を2拍目、3つ目を3拍目、4つ目を4拍目、という言い方をします。
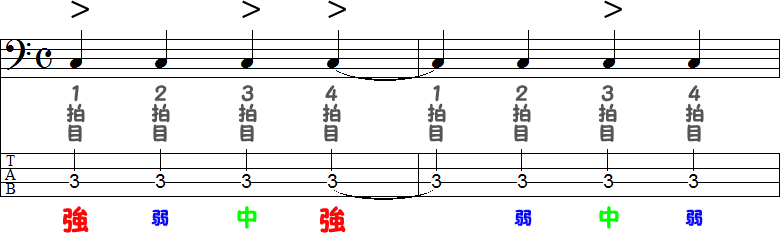
拍子記号で変わる拍
1拍目には強拍、2・4拍目には弱拍、3拍目には中強拍が入り、これを小節毎に繰り返します。しかし、これは4分の4拍子の強・中・弱の並び方で、拍子記号により変わります。幾つかの例を挙げてみます。
-
4分の3拍子の強拍・弱拍 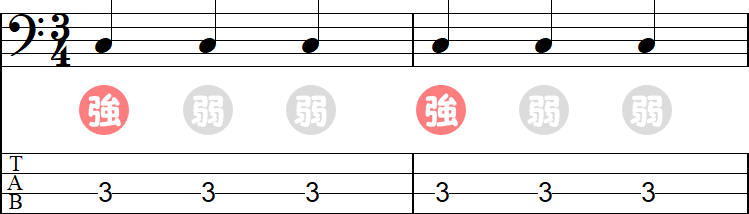
-
4分の2拍子の強拍・弱拍 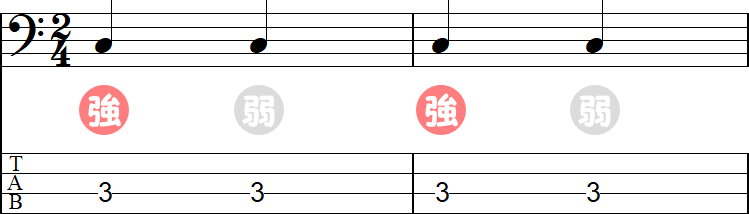
-
8分の6拍子の強拍・中強拍・弱拍 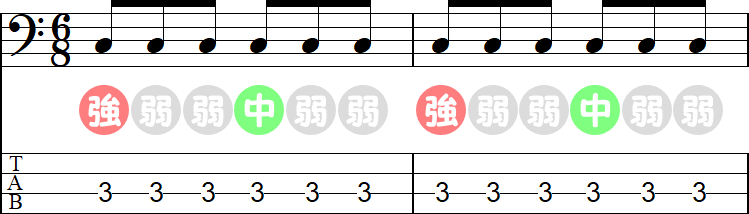
1拍目の強拍は共通
❶は4分の3拍子、❷は4分の2拍子、❸は8分の6拍子で、拍子記号により拍の感じ方が違います。しかし、どれも1拍目は強拍になるのは、共通しているのが分かります。
-
3拍目が中強拍(4分の4拍子) 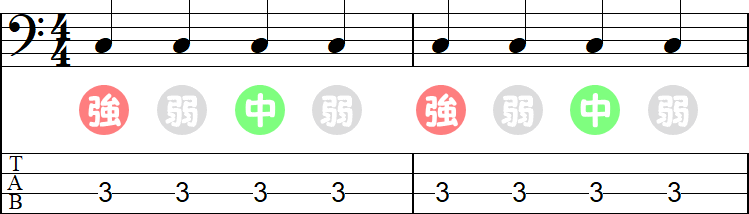
-
3拍目が強拍(4分の4拍子) 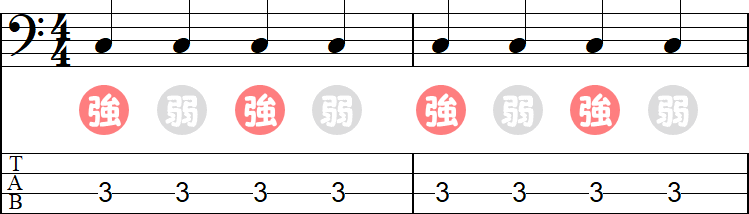
-
3拍目が弱拍(4分の4拍子) 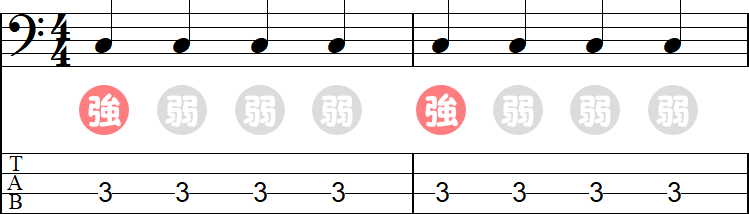
3拍目の拍の感じ方
話を4分の4拍子に戻しますが、❹は先述した3拍目が中強拍で、これが基本とされます。しかし、子供用の楽典などでは❺の、3拍目は強拍とする場合もあります。そして、私が音楽学校時代に教わったのが❻の、3拍目も弱拍とする場合で、先ずは1拍目を強拍と感じさえすれば良し、とする考えです。
強拍は強く弾くのが正解?
名前の通り強拍を強く弾く、というのも間違いではありません。しかし、強拍はドッシリと重く感じる拍、という意識を持つ方が良いでしょう。その事により僅かに溜めが生まれ、自然な音量アップにも繋がると思います。また、強拍の感じ方は曲のテンポにも、左右されるはずです。
表拍と裏拍
-
4分音符のオモテとウラ 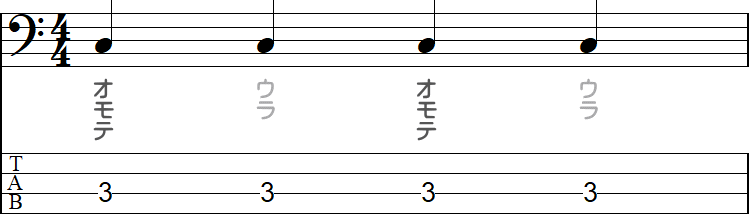
-
8分音符のオモテとウラ 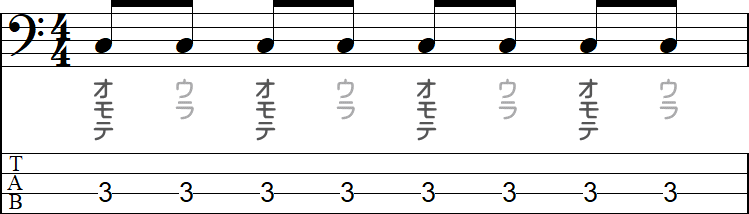
-
16分音符のオモテとウラ 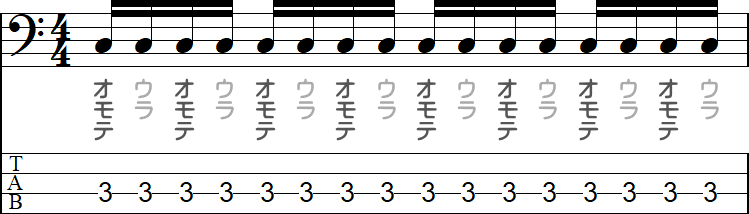
オモテ拍とウラ拍
強拍の事を表拍(おもてはく)、弱拍の事を裏拍(うらはく)、と言ったりもします。それぞれ❶の4分音符、❷の8分音符、❸の16分音符が並ぶ場合など、オモテとウラという表現をしますが、よく使われるのが❷の、8分音符の時かと思います。そこで若い頃の私は、次のような疑問を抱きました。
-
4分音符の強拍・中強拍・弱拍 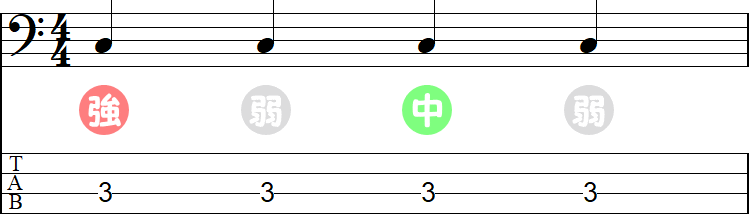
-
4分音符のオモテとウラの数値化 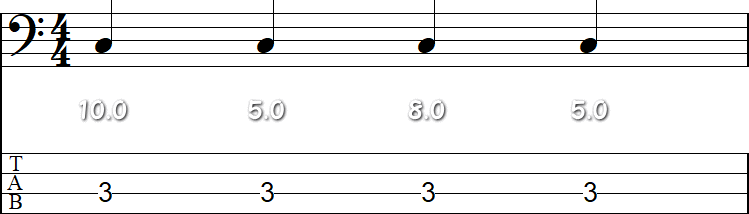
-
8分音符のオモテとウラの数値化 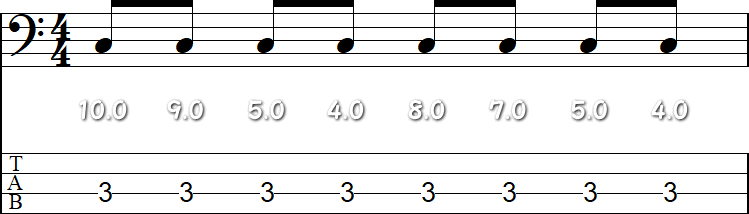
同じウラでも大きさが違う?
❹は4分音符の強拍・中強拍・弱拍ですが、これを独自に数値化したのが❺です。そこから❻の8分音符にしてみると、例えば1拍目と2拍目のウラとでは、大きさが異なるのでは、と音楽学校時代の先生に尋ねると「それも間違いではないけど、そんなに細かく考える事はないよ」と言われました。
-
表拍と裏拍を同じ音量で弾く8分音符 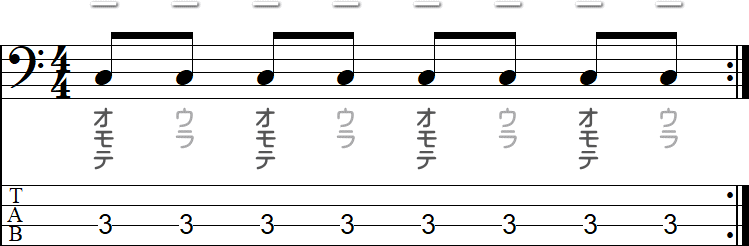
-
表拍にアクセントを置く8分音符 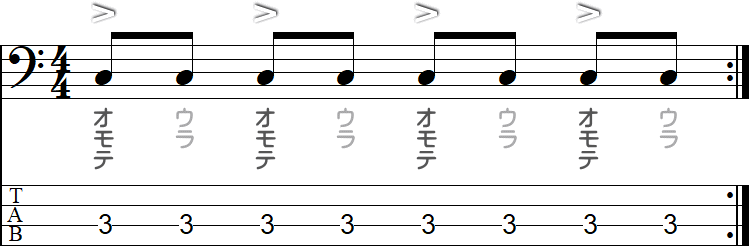
-
裏拍にアクセントを置く8分音符 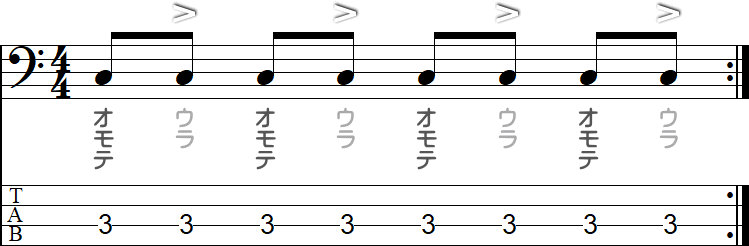
オモテもウラも同じ音量
音量に関して言えば、❼のオモテとウラを全て、同じ音量で弾ける事が重要です。これを音の粒を揃える等と言い、先ずはこの練習を繰り返しましょう。それが出来るようになったら、❽の表拍にアクセント、❾の裏拍にアクセントを置いたりする、意図的な弾き方が出来るようになります。
アクセントは楽器で違う
バンドで同じ曲を演奏するとして、楽器毎のアクセントは、異なる場合も多々あります。例えばドラムなら、バックビートと言われる、2・4拍目にスネアを叩いて、アクセントをつけるのが、ポピュラー音楽の基本なので、ベースのアクセントとは違ってくるわけです。
シンコペーション
-
4分音符の強拍・中強拍・弱拍 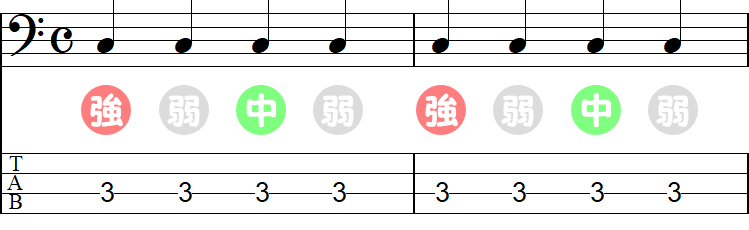
-
中強拍のシンコペーション 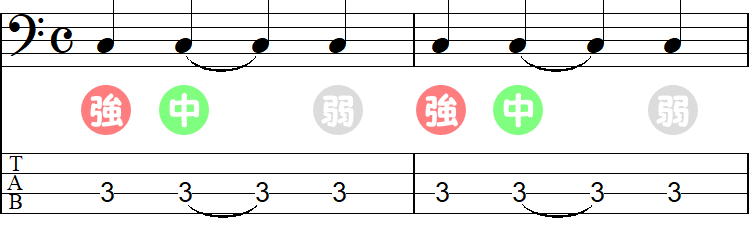
-
強拍のシンコペーション 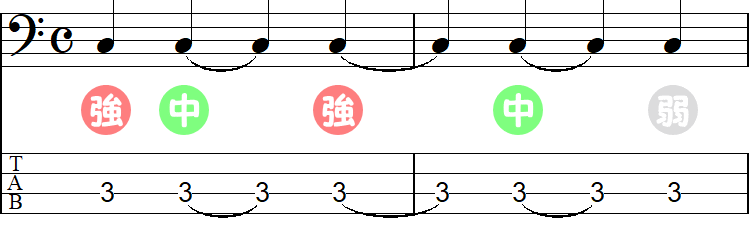
タイ記号で先取る強拍
❶は4分音符の強拍・中強拍・弱拍ですが、2拍目にタイ記号を付けると❷のように、3拍目の中強拍が2拍目へ、先取るように移動します。同じく❸のように、1小節目の4拍目にタイ記号を付けると、2小節目の1拍目の強拍が、1小節目の4拍目へ移動します。この現象をシンコペーションと言います。
-
8分音符の強拍・中強拍・弱拍 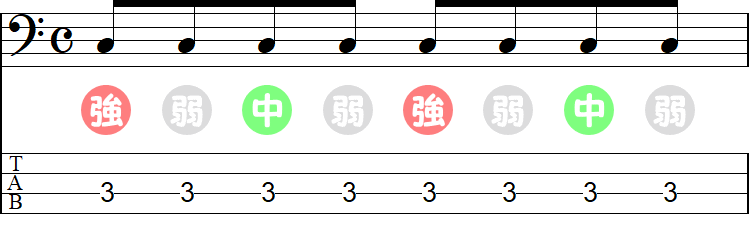
-
強拍のシンコペーション 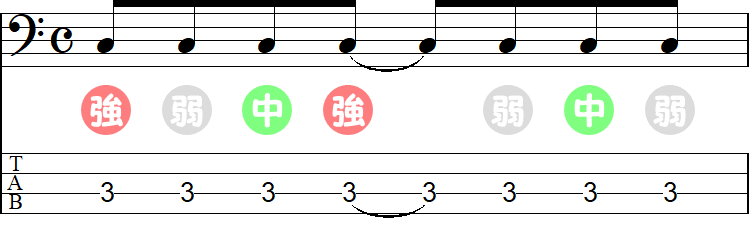
8分音符もシンコペーション
次は8分音符の強拍・中強拍・弱拍が、❹のように並んだとします。そこから2拍目のウラにタイ記号が付き、3拍目にオモテに繋げられると、❺のように3拍目の強拍が、2拍目の弱拍に取って代わり、ここでもシンコペーションが起こっています。
-
8分音符の強拍・中強拍・弱拍 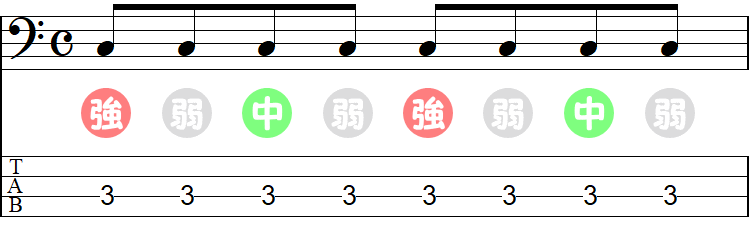
-
1・3拍目のウラにタイ記号 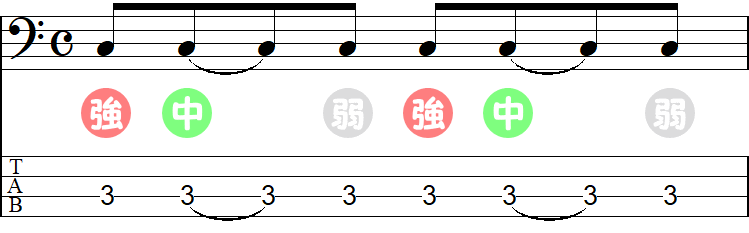
-
正しい音符の表し方 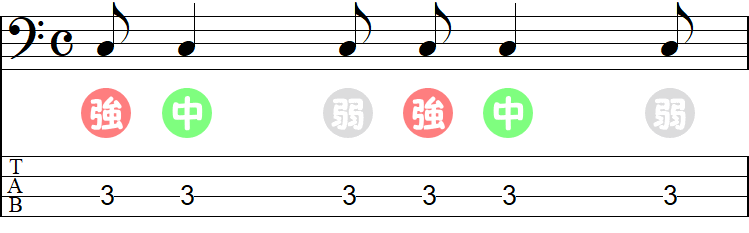
タイ記号だけではない
ここでも先ず8分音符の拍が、❻のように並んだとします。そこから1・3拍目のウラから、タイ記号で次の音に繋げると、❼のように中強拍が移動しますが、これの通常は❽のような、音符の表し方をします。このように、シンコペーションが起こるのは、見た目がタイ記号だけに限りません。
-
8分音符の強拍・中強拍・弱拍 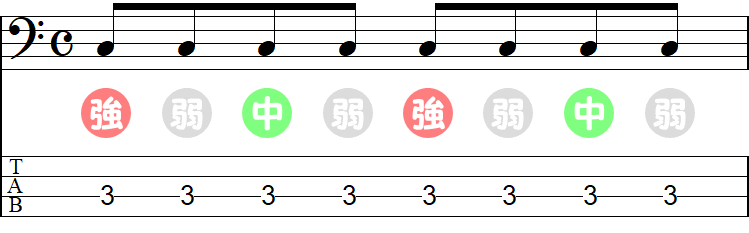
-
1・4拍目のオモテにタイ記号 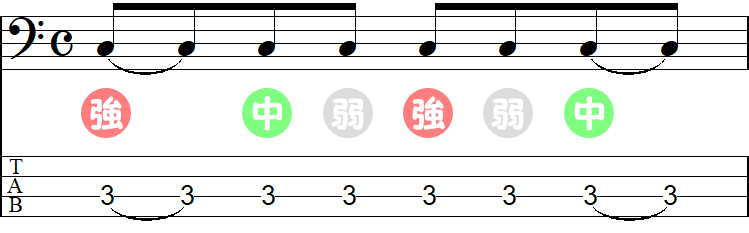
-
正しい音符の表し方 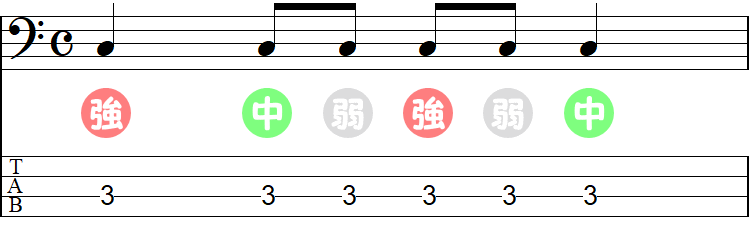
弱拍は移動しない
今度も8分音符の拍が、❾のように並んだとします。そこから1・4拍目の強拍と中強拍から次の音へ、タイ記号で繋げてみたのが❿で、正しく表したのが⓫です。こういう場合、強拍と中強拍はそのままで、弱拍に入れ替えては駄目、とは言えませんが、弱拍は移動しないのが通常です。
シンコペーションはタイ記号
シンコペーションの多くは、タイ記号から起こるので、タイ記号があれば強拍と感じて弾く、という意識をしていれば、先ずは良いと思います。
シンコペーションの練習
大きな譜面を開く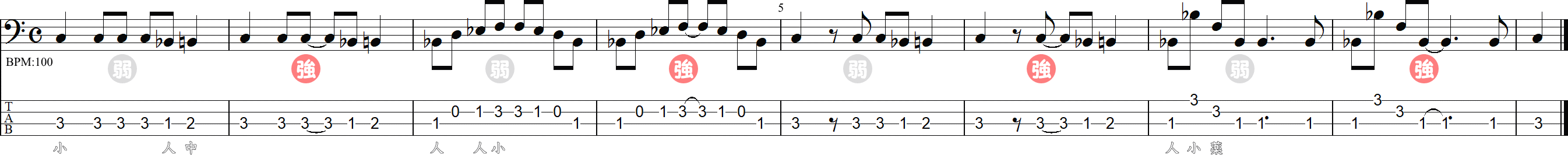
タイ記号のリズム練習
シンコペーション以前に、タイ記号のリズムが難しい、と思う人も居るはずです。タイ記号に慣れる練習として、先ずはタイ記号を外して考える、というものがあります。上記の譜面では1・2小節目、3・4小節目、5・6小節目、7・8小節目が、そうなっているので、これを利用して練習してみましょう。
大きな譜面を開く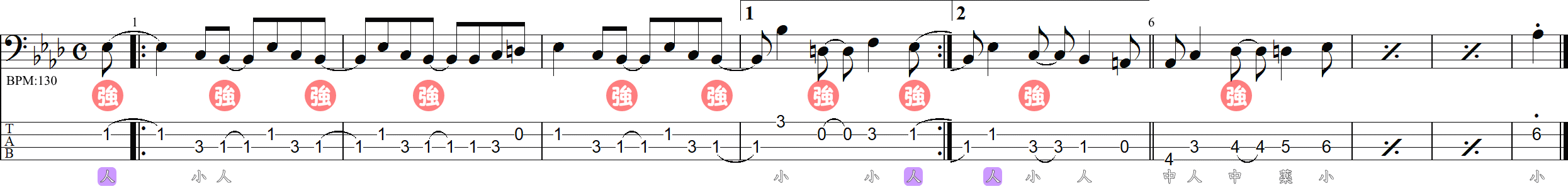
入り方もシンコペーション
全体的に難しいベースラインですが、先ずは入り方に難しさを感じます。この部分も次の1拍目の、強拍が移動してくる、シンコペーションとなっています。言葉で説明すると、4拍目のウラから入りますが、それよりも先ずは、音源を何度か聞いて、声に出して歌ってみるのも、良い練習になります。
始まりの不完全小節
上記の譜面のように、8分音符だけ等の小節を、不完全小節と言います。不完全小節は小節数に数えないので、次からを1小節目とします。最終小節が不完全小節の時もあり、それは小節数に数えます。
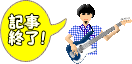
- 拍には強拍・中強拍・弱拍、という種類がある。
- 強拍は重くドッシリ感じる拍、という意識を持つ。
- シンコペーションは強拍が、前に移動してくる現象。